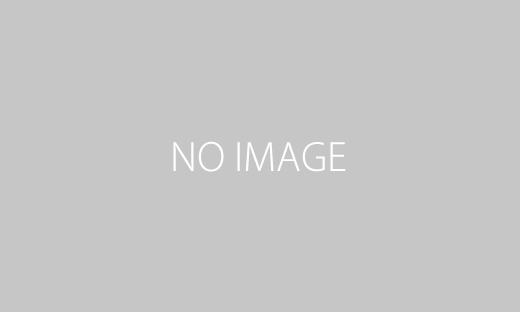【事業報告】人づくり・地域づくり関係職員等研修講座(前沢会場)
実施日:令和5年9月6日(水)
事 業 報 告
公民館等が多様な主体と連携・協働する意義について理解を深めるとともに、持続的な地域づくりの在り方を学ぶことを目的に、研修講座を開催しました。公民館・地区センターや県、市町村の生涯学習・社会教育関係職員、地域づくり関係職員等33名が参加しました。
【事例発表】「住みたい、住み続けたい!『きたまた』にまた来たい!」
まず、令和4年度優良公民館表彰優秀館である奥州市北股地区センター 事務長 髙橋 進 氏より事業、取組について発表していただきました。北股地区では急激な人口減少や農村集落機能の低下等、多くの課題を抱える中、学生との協働等の 特色ある地域活動が展開されています。1つ1つの取組に施された工夫はもちろん、髙橋氏の「イベント型では持続しない」「『ニーズ(手伝ってほしい)』と『シーズ(手伝える)』のマッチングが大切」「学生は応急手当。目的は地元住民が主体で地域をつくること」などの言葉に、多くの参加者は頷きながら聞き入っていました。

[ 北股地区センター 事務長 髙橋 進 氏 ]
次に、岩手県立大学ボランティアサークル「北股フレンズ」代表 及川 駿斗 氏より、サークルの活動を紹介していただきました。ワークキャンプ等の活動を通し、集落内のニーズと学生のシーズを結び付ける仕組みづくりに尽力するだけでなく、北股の魅力を存分に味わって活動している様子が伝わりました。

[ 岩手県立大学ボランティアサークル「北股フレンズ」 代表 及川 駿斗 氏 ]
最後に、岩手大学教育学部 准教授 深作 拓郎 氏より、「『学生が来たから地域が持続している』訳ではないところがすごい。地区振興会が主体的に課題やニーズを把握し、学生との化学反応で地域が活性化している」との助言をいただきました。

[ 岩手大学教育学部 准教授 深作 拓郎 氏 ]
【講義・演習】「継続的な地域づくりのための連携・協働とは」
引き続き深作氏に講義・演習のご指導をいただきました。提示された事例やグループでの話し合いを通して、「サービス化」社会の進展によって人々のつながりの希薄化という課題が深刻化しているという現状を理解することができました。また、深作氏が自身の研究成果をもとに、住民が主体となり持続可能な地域活動を実現するために、「目的・目標や『リスク』を含めた完成までの過程の共有」や、「呼応しあえる・共響しあえる関係」づくりが重要であることや、「すべての人々がコミュニティに参加できるしくみづくり」が社会教育行政に求められていることについて言及されました。
現代的な地域課題や子どもの居場所づくりを通じた地域づくりについての豊富な知見や実践経験をもとにしたお話により、参加者の学びがさらに深められた貴重な時間となりました。

[ 深作 拓郎 氏 ]

[ 講義・演習での受講者の様子 ]

[ 講義・演習での受講者の様子 ]
【受講者の声】
- 多世代、様々な価値観同士の巻き込み方も示唆に富んでいた。
- 北股地区振興会の取組は素晴らしく、同じ課題を抱えている地域の刺激的なお手本となると思った。
- 地域活性化のためには、外部からの助けも必要だが、地域住民の意識も高める必要があると思った。
- 行政はあくまでもサポート、地域が主体となり、地域の中で循環できる関係性が大切だと学んだ。
- イベントがゴールではなく、スタートラインであること、それを機会として拡げること、持続することが重要であることを教えていただいた。
- 地域で「呼応・共響」しあえる関係をつくるにはどうしたらよいか一緒に考えていきたい。
- 社会教育の重要性を改めて感じた。
【受講者の評価】
A(有意義) 94%
B(どちらかといえば有意義) 6%
C(どちらかといえば有意義でない) 0%
D(有意義でない) 0%
【担当者から】
多様な地域課題の解決と持続可能な地域づくりを実現するために、社会教育を基盤とした「人づくり・つながりづくり・地域づくり」が大きな役割を果たすことを再確認することができました。今回の研修会での学びを、住民主体で持続可能な地域活動の活性化のためのヒントとして活かしていただけたら幸いです。