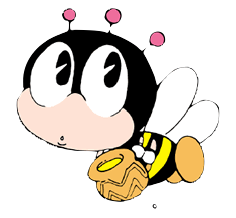

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 思春期編
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
思春期編
|
(1)家庭生活の本質 (2)大切にしたいこと (3)生活リズム (4)思春期の心 (5)第二次性徴 (6)子どものストレス (7)無防備なセックス (8)わが家の味 (9)中2の学校生活 (10)学校週5日制 (11)進路指導 (12)勤労意欲 (13)いじめの対応 (14)不登校を始めた時 (15)社会の問題に目を (16)ストップ・ザ非行 (17)ボランティア活動 (18)中学生の人権 (19)環境教育 (20)地域活動へ参加 (21)父母の役割 (22)親子のだんらん (23)夢を語り合う |
(1)家庭生活の本質子どもを一人前の人間として自立できるように育てることは、家庭の大きな責任です。 身の回りのことだけでなく、精神的にも経済的にも自立することが求められます。 しかし、経済面ばかり注目し、「よい職につくためには、勉強さえできればよい」という風潮もあり、 精神面を育て、自立させることは軽視されがちです。また、核家族化や少子化など家族形態の変化に よって家庭の教育力が弱まり、親は子育てに自信がもてなくなっています。 赤ちゃんがこの世に産声をあげたとき、はじめて出会ったのは、母親や家族です。 子どもは、身近な人への信頼関係を深め、よりどころにして成長し、やがて思春期を迎え、 自立への最終段階を迎えます。 この時期は、親や大人を批判し、困らせているかもしれませんが、順調に育ってきている証拠です。 無理難題や青臭い論議も、親を信頼しているからこそ話かけてくるのです。 また、親がどんな対応をするのか確かめているのかもしれません。 自分の思春期の経験を語ること、子どもの抱えている問題を子どもの側に立って一緒に考え悩むこと、 これは身近にいる親だからこそできることです。正解はでなくても、子どもの気持ちを真剣に受け止める姿勢が、 信頼の基盤となるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ -親の役目はものさしづくり- 親として、お金や土地などの資産を残すよりも、ものごとの見方、考え方の基準となるものさしを きちんとつくってあげましょう。 無理難題や青臭い議論も、親を信頼しているからこそでは… ページの先頭に戻る (2)家庭生活で大切にしたいこと「我が家に帰るとほっとする」誰もが感じることです。 これは、自分の家では、気ままが許されるということではなく、家族同士がつくってきたルールを みんなが守っているという安心感があるからなのです。「家風」といえば少し古臭いですが、 我が家のルールは、親の価値観と家族の話し合いから生まれます。 子どもにとって家族は、一番身近で多少の甘えも許される場所です。 家族にしかいえないこと、家族だから理解できることもたくさんあります。しかし、子どもの気持ちをくみ取って、 世話をやき過ぎるのもいけないのです。家族であっても、言葉にして気持ちを伝え、 コミュニケーションの能力を高める機会としましょう。 「さあ、話し合いの時間です」と構えるのではなく、親が率先して、日常的なあいさつ、 出かけるときの声がけを始めてみませんか。子どもは、表情やしぐさでコミュニケーションを とっている場合もあります。 子どもが話しかけてきたときは、チャンスを逃さず、じっくりと話を聞いてあげたいものです。 いつも「から返事」では、いい加減にあしらわれていると感じ、「話したい」という気持ちが なえてしまうものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆
ページの先頭に戻る (3)おたくの家庭生活のリズムはどうですか人間の体や脳は、目覚めてから約2時間後にようやくバランス良く働き出すといわれます。 学校の授業もちょうどその条件のよい時間帯に設定されています。 もし、遅く起きて、学校到着が目覚め30分ぐらいしかたっていなかったらどうでしょう。体も脳も、 朦朧(もうろう)とした状態です。登校時の交通事故や学習に集中できないなど、 心配なことがたくさん考えられます。おまけに「朝食抜き」ということになれば、 脳はすっかりお休み状態です。朝食は、脳への最高の栄養といわれます。しっかりとした朝のスタートは、 その日をしまりのあるものにしています。 さらには、夕食後の生活を工夫してみましょう。学習時間、テレビの視聴、友だちとの電話など、 自分の必要とする時間を決めて上手に使っていく力を育てたいものです。これは大人になったとき、 仕事を能率的に処理していく力になります。 食事やだんらんなど、家族共通の時間をはっきりさせるとともに、自分の時間については、 しっかりと責任をもたせましょう。もちろん親も同様です。朝起きの声がけの回数は、子どもと約束し、 それ以上は、心を鬼にして我慢してください。何回かの失敗は覚悟の上です。 自由な時間を保障しながらも、家族全員がそろう時間を軸にした家庭生活でありたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 我が家には我が家の決まりがあり、これだけは譲れないという、最小限のものは貫きましょう。 ページの先頭に戻る (4)思春期 ~揺れ動く心~思春期にある中学生の時期は、心身ともに大きく成長し、 身体的にも心理的にも子どもから大人への移行期です。 身体的には、第二次性徴の発現を中心とする急激な変化が始まり、男らしさ、女らしさの身体的条件が整い、 この身体変化を受け入れることが一つの課題となります。 心理的には、それまでは素直に受け入れてきた親や教師など身近な大人の言動に対し、反抗的になります。 これは、第二反抗期といわれるものであり、自立するためには避けて通れないものです。 自己意識が強まり、「自分は、一体何ものであるか、自分は何をしようとしているのか」という 大きな課題に取り組むために自分自身を見つめながら、大人から距離を置こうとする一方で友人と より親密な交友関係をもとうとするのが、この時期の特徴でもあります。 思春期は、たくさん悩み、反抗し、自分で考えながら大人として自立していく大切な時期です。 大人にできることは、子どもを信じて見守りながら、ともに考え、理解することです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 少し離れて見守る、心のゆとりをもちましょう。干渉し過ぎは、子どものためにも、 親のためにもなりません。 子どもの思春期は、親にとって、子離れの時期です。 ページの先頭に戻る (5)二次性徴の発現 ~中学生の身体的発達の特徴~-二次性徴の発現 ~中学生の身体的発達の特徴~- 思春期は、第二次性徴とともに始まります。男女の違いがなく発達してきた子どもが、女子は10歳ぐらい、男子は12歳ぐらいから急に身長が伸び始め、男女によって体つきや生理現象にも違いが見られるようになります。これを第二次性徴といいます。その発育、発達の速度や程度には個人差があり、周りの人と比べて心配する必要はありません。体内のホルモンのバランスが変わるためイライラしたり、身体の変化にとまどい、悩むこともあるでしょう。異性への関心が芽生え始めるのもこの時期です。 -思春期の体の変化- 思春期は、ホルモンの働きにより、生涯を通して一番ドラマチィックな性成熟がおこる時期です。 女子は卵巣の発達により月経が始まり、男子は精巣の発達により精通が始まります。 成長ホルモンは、脳下垂体から分泌されるホルモンで、骨、筋肉、内蔵、皮膚、毛などの成長を促進します。 性ホルモンは、精巣や卵巣から分泌されるホルモンで、体つきを変化させたり、生殖器の発育を促進させます。
外見は大人でも、まだまだ子どもです。 お父さん、お母さん、しっかり目をかけ続けましょう。 ページの先頭に戻る (6)子どものストレスを解消するために友人と話をした後やスポーツをした後、気分が軽くなるとかすっきりするといった経験は、 誰もがもっていると思います。 この言葉に出して話す言語化と体を動かす行動化が、ストレス解消の二つの柱となります。 言語化は、友だちだけでなく、家族や、場合によってはペットに向かって話すことで、 行動化はスポーツ以外にも友だちと一緒にゲームをしたり、家族でキャンプに行くことでストレスを解消します。 しかし、信頼できる家族や友人がいないと、うまく言語化や行動化ができなくなり、家庭内暴力や非行、 いじめなどの非社会的行動化をおこすおそれがあります。また、そのストレスの攻撃性が内側(自分)に 向けられたときには、神経症や心身症といった精神症状をおこします。 ストレスを言語化や行動化で解消することは、誰にとっても大切なことですが、 思春期という嵐の中でストレスを受けやすい状態の中学生にとっては、特にも必要なことです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもが電話で長話をして困るといった話をよく耳にします。ある程度は、 大目に見てやることも必要です。 ページの先頭に戻る (7)無防備なセックス「愛していればセックスするのは当たり前」という風潮が若者たちの間に見られ、 セックス経験のある中学生の割合は10%を超えています。「うちの子に限っては」とか、 「まだ子どもだからそのようなことはしない」と思っている親も多いと思いますが、この現実に対し、あまりに無防備といえます。 妊娠してしまい、産婦人科を受診した中学生の両親が、「まさか自分の娘がそのようなことを するとは思わなかった」という話もあります。 子どもが中学生になったら、「男の子に対しては父親」が、「女の子に対しては母親」が、 「望まない妊娠を防止するため、性感染症にかからないため、セックスをしてはいけない」と きちんと伝える必要があります。 今、行われている避妊法で100%完全な方法はなく、エイズをはじめとする性感染症の危険性もあります。 もし妊娠してしまえば、その子どもの心には大きな傷が残り、性感染症にかかれば、 治癒した後でも血液検査でわかる痕跡が一生消えずに残ります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 無防備なセックスが行われたとき、72時間内であれば、産婦人科で緊急避難ピルを処方して もらうことができます。早ければ早いほどよいのですが、二錠服用することで、 有効率97%とかなり効果があります。 ページの先頭に戻る (8)わが家の味「食べる」ということは、生命の維持だけでなく、「共食」を通して人間的な結びつきが生じ、 「おいしい」「楽しい」という心理的な満足感を与えるものです。市販の惣菜は、手軽で便利ですが、 味に飽きることはありませんか? 家庭のおかずは、知らず知らずのうちに、家族一人ひとりの好みや体調、天候、前日の献立をもとに、 味付けや食材の組み合わせが工夫がされ、飽きることないのです。ときには、失敗もありますが、 次へのステップですし、食卓の話題づくりに一役買うでしょう。 共働き家庭が増え、食事づくりに時間がかけられず、つい市販のお惣菜に頼りたくなります。 市販品には保存料・添加物など、長い目で見ると不安な材料が使われていることがあります。 少量でも、成長期の子どもには、これから長い間摂取していくことを考えると、新鮮な材料を使って 責任のもてる食事を与えたいものです。 大人ばかりでなく、子どもの生活も忙しくなり、時間を決めて家族そろって食事をすることが難しく なってきています。家族そろっての食事は、共通の話題を深めるチャンスであり、楽しい食卓となります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ お弁当は親から子どもへのメッセージ 「3年間、毎日のお弁当づくりありがとう。おいしかったよ」卒業式の会場にいた母親たちの苦労が 報われた一瞬でした。 ページの先頭に戻る (9)中学2年生の学校生活~中学生の意識調査から~ 中学2年生は、学校生活をどのように感じているのでしょうか。 平成12年に県教育委員会が行ったアンケート調査によると、全体の約半数の子どもたちが、 「学校生活は忙しい」と回答しています。その理由として、「クラブ活動(部活動)や スポーツ少年団活動が忙しいこと」を一番にあげており、次いで、「勉強することが多い」 「休み時間が少ない」などをあげています。 では、中学2年生は、今、何を一番がんばっているのでしょうか。「あなたが、 今がんばっていること」という問いには、学校生活が忙しいと感じる理由で最も多かった 「クラブ活動やスポーツ少年団活動」が一番で、「自分の興味あることに取り組むこと」が 二番目になっています。 これらのことから、本県の中学2年生は、クラブ活動や少年団活動によって、学校生活が忙しいと 感じているものの、今打ち込んでいるのもクラブ活動やスポーツ少年団活動であることがわかります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 活動の目的や目標を明確にすることや活動に取り組む価値を見出すことが、活動意欲を高めます。 ページの先頭に戻る (10)学校週5日制を有効活用しよう学校週5日制は、学校、家庭、地域社会での教育や生活全体で、子どもたちに「生きる力」をはぐくみ、 すこやかな成長を促すものです。 土曜日や日曜日を利用して、家庭や地域社会で子どもたちが、さまざまな生活体験や社会体験、 文化・スポーツ活動などをすることが望まれています。 文部科学省の調査では、「小さい子を背負ったり、遊んであげたりする」「果物の皮をむいたり、 野菜を切ったりする」「昆虫を捕まえたり、魚を釣ったりする」などの生活体験や自然体験の豊富な子どもほど、 「友だちが悪いことをしていたら、やめさせる」「バスや電車で席をゆずる」などといった道徳観や正義感が 身についているという結果がでています。 県や市町村などでも、子どもたちが休みの日を有意義に過ごせるように、さまざまな体験活動の場や 機会の充実に努めています。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 県や市町村の広報誌や各学校の広報には、体験活動の情報が掲載されています。親子で参加できる 活動を探してみませんか。 ページの先頭に戻る (11)進路指導-進路は親子の語らい- 中学2年生になると1年生のときとは違い、どうしても自分の進路や受験について意識し始めます。 将来について考える最初の時期ではないでしょうか。 親子で、進路や受験の話題になると、「希望する高校=予想合格点」という話し合いに 終始してはいないでしょうか。 親はややもすると、「子どもがテストで何点とったか」「クラスで何番目か」などと他の子どもの点数との 比較に目を奪われがちになります。親の期待からだけで子どもを評価することは、 子どもたち一人ひとりの個性や成長のためによくありません。 中学2年生は、子どもとしての一面をもちながらも、内面は鋭い知性と感性をたくわえつつある 時期でもあります。ともに人生を語り、生活を共有できる年齢になっていることに気づいてほしいものです。 この時期、子どもたちは、周囲からのアドバイスや親子の会話によって、 自分自身も知らずにいた新たな能力や適性に気づくことが多くあります。 子どもの意志を尊重しながら、進路や受験、将来について大いに語り合いたいものです。 将来を見とおし、自分の好きなもの、打ち込みたいものが見えるようになると、勉強は、 単なる受験だけにあるものではないという自覚も芽生えてきます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもには子どもの人生があります。常に親の価値観だけで方向を決めていると、 子どもは独自の価値観を形成できなくなってしまいます。 ページの先頭に戻る (12)地域が育てる勤労意欲今、中学生は、地域に目を向け、地域に学び、地域で育っています。 中学生時代は、大人への一歩を踏み出す重要な時期です。 家庭や学校、地域社会で出会うさまざまな体験が人間形成の貴重な糧となり、 進路を決定する能力や態度を育てます。 多くの中学校では、「まちとの関わり」「人との関わり」をねらいとして、地域での職場体験や ボランティア活動を行っています。子どもたちは、社会体験を通じて地域社会との つながりを学んでいます。 ある職場で体験学習を終えた子どもは、「働くことの大変さ、社会人として身に つけておかなければならないマナーの大切さを理解した」と感想文に記しています。 また、親の職場を訪問見学した子どもは、「親の働く姿に感動し、仕事の厳しさを知った」と 感想を述べています。 このように多くの子どもたちは、働くことや社会に奉仕することによって得られる達成感や 喜びを体得しています。地域において、多くの社会体験を重ねることは、 自分の職業の適性や将来設計について考えるよい機会となっています。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 学習も仕事も人生も、汗を流し、失敗を重ねながら達成していくものです。子どもを、 励まし、温かく見守っていきましょう。親は子どもの応援団です。 ページの先頭に戻る (13)子どもの心を早くキャッチしよう~いじめに対する親の対応~ 【いじめのパターン】 いじめには、身体的暴力、金品・物品の強要、無視・仲間はずれ、一見悪ふざけに見える行為・ からかい・ひやかし等さまざまなパターンがあります 【いじめは早期発見が大切】 いじめにあった子どもの多くは、誰にもいえずとても悩んでいます。また、いじめを受けている 子どもはさまざまな理由でそのことを知られないように隠します。 しかし、どんな場合でも子ども自身から何らかのサインがでているものです。いじめに対する指導は、 早期発見が大切です。子どものサインを大人が見逃さないように気をつけるのが大切になります。 子どもの変化に気をつけましょう。 【いじめに気づいたときの対応】 いじめに気づいたときは、子どもが追いつめられている気持ちをまず受け入れ、 心から安心できる環境づくりと子どもの味方になるという姿勢を崩さず対応していくことが大切です。 いじめに気づいたら、すぐに担任に子どもの悩みを正しく伝え、解決の方法を一緒に考えましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆
(14)子どもの心を早くキャッチしよう~子どもが不登校を始めたとき~ 子どもが身体的な病気とは思えないのに学校に行かなくなったとき、親は驚き、とまどい、 そしてどうしたらよいかわからず、立ちすくんでしまうのではないでしょうか。 このようなときどのようにしたらよいでしょうか。 明かな身体疾患がなく、学校を休みだした場合は、躊躇(ちゅうちょ)せずに小児科の診察を受けましょう。 身体の病気がないかどうか、きちんと調べてもらうことが大切です。学校に行かなくなった、 行けなくなった子どもの35%に身体の病気が見つかり、それを治療することで登校できるようになっています 。身体の病気の中には、起立性調整障害のように不定愁訴が多く、普通に見ただけでは身体の病気とは 思えないものもあるので、単純に不登校と決めつけるのは大変危険なことです。 学校に行けないのは、身体の病気ではなく、心因性の不登校と考えられたときでも小児科医は 心因と理解した上で、あえて今でている身体症状に対応します。そして心因性の原因が深く、 カウンセリングが必要なときはカウンセリングを受けるようにしましょう。 誤解している人が多いようですが、子どもの心に異常があるので精神科医に診てもらうわけで、 不登校児に何かよいアドバイスをしてもらうために臨床心理士がカウンセリングをするのではないのです。 臨床心理士は、子どものよき理解者、話し相手としての専門家なのです。不登校は人との関わりの中で しかいやすことができないのですが、カウンセラーは人との関わり合いが途切れそうになっている 不登校の子どもの心をつなぎとめ、子ども自身が何らかの意味での転機、契機などをつかんだり、 発見したりするまで子どもの心を支えます。 不登校が始まり2ヵ月以内に受診して、カウンセリング等の適切な対応を受けた例と、 2ヵ月以上たってから受診した例では、前者は平均36日で再登校できていますが、 後者は平均527日もかかっています。不登校の原因は育ち方、学校環境、社会環境が複雑に組み合ったもので、 すべての不登校児が初期に適切な対応を受けなければ早期に登校できるとは思いませんが、 初期に適切な対応を受けることで比較的早期に再登校できる子どもも多いと思います。 「登校刺激を加えない方がよい」などというをのを正しいとして、結局何もしないままでいるというのが、 一番よくないことです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆
(15)社会の問題に目を向けよう下降気味だった少年非行の発生件数が、下げ止まりの気配を見せてきています。 数ばかりではありません。質的にも凶悪化の一途をたどっています。 県内では、毎年1万人余の少年が補導されています。そのうち、中学生は約10パーセントの 1,000人余りで、窃盗、恐喝、深夜徘徊、急性アルコール中毒、出会い系サイトからみの 性非行等で補導されています。自己の欲望にのみ従順で、家族や被害者の苦しみなどに、 彼らの想像力は及びません。 犯罪被害少年の問題も深刻です。全国では、平成12年中に17人の中学生が犯罪の被害で命を落とし、 146名が強姦の被害にあいました。事件や事故、災害等によって心に深い傷を負った被害者は、 長い年月をPTSD(心的外傷後ストレス障害)によって苦しむといわれています。 社会の動きや身の回りの出来事に関心をもち、家族で話し合う習慣をつくりましょう。 現実におきている問題について語り合うことは、一種のシミュレーションともなり、 心のブレーキ機能やセキュリティを高めることにもつながります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 普段から、家族で緊急時の連絡方法、緊急避難の場所・方法等を取り決めておくと、 いざというときに威力を発揮します。 ページの先頭に戻る (16)ストップ・ザ非行!「シンナーはダメだけど、ライター用ガスはいいんだよね」「お金をもらったら売春だけど、 物はいいんだよね」という中学生がいます。 中学2年生は、思春期の真っただ中で、心も身体も、これ以上ないというくらい、 不安定で揺れ動いています。だからからこそ、支えてくれる確かな何かがほしいのです。 別の言葉でいえば、自分を正当化してくれる理論的なよりどころです。「シンナーはダメだけど…」も その一つです。非行は、こうした、人づてに聞く不確かな情報やうわさ話が入り口になって いることも少なくありません。 中学2年生にもなると、ITの操作能力は大人より優れているかも知れません。一方、 うわさ話などのアナログな情報に翻弄(ほんろう)されているのも事実です。今、中学生の間には、 酒・煙草、薬物、性に関する誤った情報が広まっています。病気になって初めて、 ことの重大さに気づく中学生が大半です。無知は最も危険です。正確な知識はセキュリティの基本。 今こそ、親として正確な知識と情報の伝授に心がける必要があるのではないでしょうか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親が構えると子どもも構えます。大切なことほど事実に即して淡々と話してみましょう。 「君はどう思う?」と聞いてみるのも効果的です。 ページの先頭に戻る (17)自らを成長させるボランティア活動「ボランティア=人のために何かをする」というイメージが多いかと思います。 さて、本当にそうでしょうか。ある生徒の作文です。 私は、そのおばあさんを見ていて、「何かしてあげたい」でも、何をしてあげればいいのか わかりませんでした。そのとき、別に考えることじゃなくて、「してあげたいことをしてあげればいいのだ」 と思い……。私のできることは、これくらいしかなかったからです。 でもそのおばあさんは、何回も「ありがとう」「ありがとう」といってくれました。 十分な介護をしてあげたわけでもないのに、「役に立てたかな」と思い、 私にとっては小さな小さなことだと思っていたことが、おばあさんにとっては嬉しくて、 してあげたことがありがたいことだったのだなと思うと、私まで嬉しくて泣いてしまいました。 今回のボランティアをとおして、自分なりに何かを得られたような気がします。 家のおばあさんは、「うるさい」と思ってばかりでした。でも思えば、「 みんな私のことを思って話すのだな」心配してくれて話してくれているのに「うるさい」って 思うのは失礼なこと……。そう思えたのは今回のボランティアに参加したからです。 「少年は、必要とされてはじめて、大人になる」この言葉は、ボランティア活動が、 人間の成長と自立にどのような貢献をするかについての意味を見事にいいあらわしています。 中学生が、他の人や社会の「役に立つ」存在として周囲に認められ、かけがえのない存在として 「必要とされている」ことを知る。ボランティア活動は、中学生の社会への参加意識を育てるだけでなく、 人間としての成長と自立のための手段でもあるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ボランティア活動は、社会貢献という形をとおして、自らが学ばせてもらう活動です。 ページの先頭に戻る (18)中学生の人権とは子どもの成長は、保護者にとって大きな喜びです。しかし、成長するにしたがって、 親から離れていきます。中学生のこの時期は、まさに、親から離れ一人の人間として成長するための 大切な時期といえるでしょう。 第二反抗期といわれるこの時期は、親からの自立を求め、親の考えに対して自分の考えを 主張する時期です。子どもにとってよかれという親の思いや、保護、善意、愛情の名のもとに 一方的に大人の価値観や倫理を押しつけると子どもの反抗は強くなるばかりです。 子どもには子どもの世界があります。それはときとして、大人の価値観や倫理から見れば、 悪と見えることもあり、許されないことと映ることもあるでしょう。しかし、 子どもの時代が大人の準備期間としてあるのではなく、子どもとして、その存在自体があるのですから、 子どもが子どもとして生きている時間が限りなく尊重されなければなりません。 そのためには、子どもの人格を尊重しながら、自己責任の原則のもと、自らの判断で選択し、 行動させるという環境づくりを援助することが大切です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「子どもは大人と違ったもの」であり、不完全な大人としてではなく、子どもとして 理解されなければならない存在である。(J.J.ルソー) ページの先頭に戻る (19)環境教育もし、地球が太陽にもう少し近かったり遠かったりしたら、地球には水は存在せず、 もちろん生物も私たち人間も生まれなかったでしょう。水と緑にあふれた地球は、 宇宙の中でも奇跡的な存在です。その地球が今苦しんでいます。 地球を救うことができるのは、地球人である私たちしかいないのです。地球環境を守るために、 親子でできる環境保全に取り組んでみませんか。 電気やガスなどのエネルギーを節約し、二酸化炭素の排出をおさえるために、 今日からできることがあります。「照明・電気器機のスイッチをこまめに消す」「衣服で温度調整をする」 「お風呂は続けて入る」「生ゴミはネットに集め水を切る」「合成洗剤やシャンプーは適量を使う」など です。このような行動が地球の温暖化防止につながるのです。 「混ぜればゴミ」「分ければ資源」ゴミ分別を徹底し、一人ひとりが身近にできることから 始めるしかありません。環境に優しい暮らし方について、子どもと話し合い、実践してみましょう。 暮らしの中のちょっとした心がけが、地球環境保全になるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 飲み残した味噌汁を、軽い気持ちで台所に流す。その結果、汚れた川の水をきれいにするには、 おわん7,000杯の水が必要になります。 ページの先頭に戻る (20)地域活動への参加を通して社会性を今、青少年に最も欠けているのが地域社会の一員としての体験です。そのため、意図的に地域の活動に 我が子を関わらせたり、隣近所の人たちとの触れ合いを進めたりすることが必要です。 自分の住んでいる町なのに、知らないことがたくさんあるという子どもも多いのです。 地域を知るために、親子で身近なボランティアをするというのはいかがでしょうか。 自分の町がもっと良く見えてきて、もっと好きになります。 たとえば、公園を清掃する、散歩しながら空き缶を拾う、公園のブランコなどの施設が壊れていないか、 危ない物がころがっていないか注意して見るなどの活動があります。また、中学生にとって、 図書館や博物館などの手伝いは結構面白い発見に出合ったりするものです。子どもの興味がある 公共施設から始めると効果的です。 地域からは、人間として生きていくための知恵や体験をとおして教わります。そこから学んだことから、 社会のしくみやもう一人の自分に出会うという新しい世界が広がっていきます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 毎日の暮らしの中に、ボランティア活動のヒントがたくさん隠れています。身近なところから、 できることから取り組むことが第一歩です。 ページの先頭に戻る (21)中学時代における父親、母親の役割中学2年ぐらいになると急に無口になったりするものです。そんなときは無理に根ほり葉ほり 聞こうとしないで、じっと見守っていましょう。親子というよりは「男は男同士」、「女は女同士」、 どこか伝わりあう部分が強くなってくる時期です。同性として積極的に子どもたちに関わってみませんか。 親が少年少女時代に、自分自身の失敗や戸惑いを語ることで、自分も父母と同じことを 悩んだり考えたりしていたのだということを知って、子どもは安心します。失敗を語ることによって 親の権威がおちることはありません。かえって同性として身近に感じたり、 「そんなことはしない方がいいな」などと自分を律する材料になったりするものです。 子どもの話はどんなささいなことや真剣に耳を傾けてください。反対だと思うことや とんでもない要求でも、ゆっくり時間をかけて順序立てて聴いてください。途中で口ごもったりしても、 じっと待ちましょう。しっかり向き合ってうなずいて聴いてください。子どもは話しているうちに 自分の矛盾や無理に気づいてくるはずです。そのときに父の立場、母の立場としての考えを話てください。 もちろん両親の考えは共通理解し、食い違いのないことが大切です。男子は、 そろそろお父さんとの男同士のつき合いを望み始めるものです。ここ一番というときのお父さんの 出番が要求される時期です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「聴く」というということは、子どものプライドを大切にしながら、お互いの会話を進める潤滑油です。 ページの先頭に戻る (22)親子のだんらん家族が無言でテレビを見て、番組が終わればまた無言でそれぞれの部屋へ戻っていく… 今や子ども部屋にもテレビがある家庭も多くなりました。寂しいことですね。夕食のときなど ちょっとだけ意識して家族全員で話す場を設定したいものです。食事はお腹を満たすとともに 心にも栄養を与える時間でもあります。学習と行動面の話だけではなく、自らの周囲の出来事に ついてお互いの意見を出したりすると、案外、子どもの考えがしっかりとしていることに 気づかされることがあります。 話し上手よりも聞き上手の方が対話をうまく進めることができます。子どもの言い分や考え方が 未熟だと思っても、正しいところは大いに認め、また好ましくないあり方は機嫌をそこねることを 恐れず、しっかりと目を見て穏やかに教えてあげたいものです。 ときには、親の方から相談を持ちかけ、頼りにするという姿勢を見せると、子どもは大人扱いに されることが何よりも嬉しいと思う時期ですから、かえって自分を見直すきっかけになったりします。 家族の一人として、相談にのって欲しいという姿勢を大人が見せてもいいのではないでしょうか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ○物わかりのよ過ぎる親ではちょっと心配です ○一言のよけいな教訓はなるべくさけましょう ○じっくりと聞くことで親も子も案外冷静になれます ページの先頭に戻る (23)子どもと共に夢を語り合おう現代社会のかかえる問題点に、家庭の崩壊、地域の教育力の低下、将来への見とおしのもてないことなどが あげられます。そのような社会状況の中で、子どもたちが夢をもって生き抜いていくために どんなことをしていけばよいでしょうか。 ○自立した子どもを… 夢を実現させることが教育です。夢といっても将来のことだけとは考えず、身近な目標も夢と 考えてみてください。目標(夢)を具体的に立てて、課題を実現させるための 実践活動をさせてください。それらの活動をとおして子どもの感性、知性がはぐくまれ、 今、取り組まなければならない自分自身の課題に気づき、自ら解決することが自立につながります。 ○夢を話題に… 中学時代には「夢=進学」と考えられがちですが、目標は高校進学でそれから先は またそのとき考えればよいというのでは、若く、可能性をいっぱい秘めた時期を何の目的もなく 無駄な青春時代を過ごすこととなります。 将来を見通し自分の好きなもの、打ち込みたいものに夢と希望をもって見つけることができれば 学習の目的や自分の課題がはっきりし、自分の世界を広げながら深めていけるでしょう。 そのためにも親自身が多様な価値観をもつことが必要です ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもの成長に夢をもって、目標をもたせる前に自らが生き生きとした人生を… 「親の背を見て子は育つ」 ページの先頭に戻る |