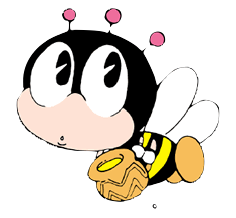

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 中学校編
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
中学校編
|
(1)社会が変わっても (2)思春期のこころ (3)中学生のストレス (4)反抗は自立のため (5)身体の発達傾向 (6)生活リズム (7)家庭の性教育 (8)大事な食生活 (9)朝食抜き (10)夜食は必要? (11)将来のことを話題に (12)勉強の環境づくり (13)再学習のすすめ (14)勉強すればいい? (15)クラブ活動 (16)良き友を持つ (17)いじめ? (18)地域の一員として (19)子離れ準備 (20)親の出番 (21)言うべきときに |
(1)社会が変わっても世の中はずいぶんと変わりました。便利なものがあふれています。楽しいことも多くなりました。 家の中ではどうでしょう。祖父母がいない家庭も増えました。家族が少なくなっただけではありません。 親も、仕事や付き合いや趣味などに忙しく、家族の顔も揃わない日が当たり前の家庭も増えてきました。 でも、どんなに忙しくても、親にとっては子どもは何にもまさる宝です。 子どもにとってこの世で最も好きなのは、親です。これは今も昔も変わりません。 家族がともに過ごす時間を心してつくりましょう。 世の中が変わった、家庭も変わったと一口に言いますが、 世の中は変わっても、「良い家庭」というものは、そんなに変わらないものです。 社会の倫理に裏打ちされた厳しさ(父性)と理屈抜きの優しさ(母性)を言葉プラス行動であらわし、 子どもを包みたいものです。父性と母性のバランスのとれた明るい家庭、これは永遠の理想像です。 このような家庭の中で育まれ、子どもから成長し、そして大人になるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「よそ様は、よそ様。これが我が家流」と胸を張れるルールを作るのもいいですね。 ページの先頭に戻る (2)ゆれる心・思春期のころ中学生の時期は思春期とも呼ばれてきました。思春期とは、二次性徴が発現してから大人として 成熟するまでの時期ですが、最近では二次性徴の発現が早まる傾向にあり、特に女子は、 小学生から生理が始まる子も多くなってきました。一方では、社会的、精神的に大人になるまで、 かなりの時間がかかるようになり、子ども、青年、成人の区分があいまいになってきています。 二次性徴に伴い、子どもはまず、性別による身体の変化に直面し、 それを受け入れることが課題となります。この時期の心身の変化は急激で、自分でコントロール できないような内的衝動に子どもはとまどってしまいます。これは、いつの時代の子ども達にも あったことですが、今日では、身体の発達に心理的な発達が伴わないのに加えて、学歴社会、 競争社会の中でのストレスが大きくのしかかってきています。大人になりたい気持ちと不安の 間を揺れ動き、将来を見通せないまま、対人恐怖や不登校といった悩みを抱える中学生も多くなっているのは 事実です。 子どものゆれる心を丸ごと受けとめられるようなゆとりを親として持ちたいものです。 ページの先頭に戻る (3)中学生の抱えるストレス仕事をする大人と同じように、中学生だってけっこうストレスにさらされています。 ひまそうに見えるのは家の中だけで、いったん外に出ると例外なく忙しいのが、いまどきの中学生。 また、一人として不安や悩みを抱えていない子はいないのが現状です。勉強に関する不安、 友達関係の悩み、容姿や能力についての劣等感、家庭生活における悩みで心が不安になっています。 それに加えて、休日返上の部活動で体もへとへとに疲れていれば、心も体もオーバーヒート。 このような不安や悩みが大きなストレスとなり、心の病気となって現れることも時にはあります。 子ども達が心のバランスを崩さずに、明るく毎日を過ごすにはどのようなことに気を付けたらよいのでしょうか。 子ども達の感じている不安や悩みの多くは、そのほとんどが、私達大人がかつて経験し、 乗り切ってきたことです。たとえ、悩んでいる様子が見られても、深刻に考えすぎずに大らかに 受けとめてあげることが大事です。先回りしすぎて、大騒ぎをしても、良い結果は生まれません。 子どもの話をじっくりと聞き、子ども自身が解決の糸口を見つけることができるよう、 さりげなくアドバイスしたいものです。ただし、決して、親の考えを押しつけたり、 親の敷くレールに無理やり乗せようとしないこと。子ども自身が自分の力で乗り越えられるよう、 陰から支えてあげましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 時には、一緒にスポーツで汗を流したり、自然を感じながら野山を歩いたり、 キャンプを楽しむこともストレス解消や親子での会話の機会を増やすことにつながります。 ページの先頭に戻る (4)「反抗」は自立のための第一歩中学生にもなると、学校や家庭での生活のほかに将来どういう職業を選択し、 社会でどのような生活をするかなども考え始めます。とは言っても、まだ、具体性はなく、 自分の方向性はまだ定まられないのが実情です。 この時期は、何でもできるような「万能感」を持つ一方、自分だけがダメなんだという 「劣等感」の間で揺れ動きます。また、周囲に対しても批判意識と依存感情で葛藤します。 こうした内面の不安定さが、身近なところにいる親や教師への「反抗」という形で現れることがあります。 本人自身、何で反抗するのかはっきりわからないでいることも多く、対処に苦慮します。 しかし、自我は、「抵抗」に出会うことで確実に育ってくるのです。「子どもの抵抗」は、 親にとっては「反抗」と言えますが、子どもにとっては親の保護からの独り立ちや自分自身の 確立という意味で、社会人になっていくための大事なステップ(親離れ=心理的離乳)となるのです。 価値が多様化し、選択肢の多い現代においては、子ども達が「抵抗」の対象を見つけることが 難しくなってきています。「ものわかりが良く、何でも子どもの言うことを聞く親」との間では、 子どもは、抵抗の対象を見出すことができず、葛藤することなく、自我も育たないまま、 成長していきます。そして、初めて、社会との関わりで抵抗を感じた時にその抵抗を乗り越えることが できず、「心身症」や「不登校」などという形で表面に出てくる場合があります。 親としての重要な役目は、子どもを保護すると同時に、社会のルールや自分の価値観、態度をはっきり示し、 子どもの抵抗の第一番目の対象となることなのです。 ページの先頭に戻る (5)身体の発達傾向男女の違いがなく発達してきた子どもが、女子は10歳ぐらいから、 男子は12歳ぐらいから急に身長が伸び始めます。これを「身長のスパート」といい、 思春期がやってきたことを示します。思春期になると体が急に発達し、性別によって体つきや 生理現象にも違いが見られるようになります。これを二次性徴といいます。その発育、 発達の程度や速度には個人差も出てきますが、一般的に女子の方が男子より2年ほど早く始まります。 ~思春期の体の変化~ 思春期は、ホルモンの働きにより、生涯を通して一番ドラマチックな性成熟がおこる時期です。 女子は、卵巣の発達により月経が始まります。男子は、精巣の発達により射精がおきます。 【成長ホルモン】 脳の下垂体から分泌されるホルモンで、骨、筋肉、内臓、皮膚、毛などの成長を促進させます。 【性ホルモン】 精巣や卵巣から分泌されるホルモンで、体つきを変化させたり、生殖器の発育を促進させます。 【女子の変化】 乳房が発達する、わきの下や性器のまわりに毛がはえてくる、 皮下脂肪が増える、腰幅が広くなる、丸みのある体つきになる、 【男子の変化】 声変わりが始まる、髭や脇の下、性器のまわりに毛がはえてくる、 筋肉が発達する、肩幅が広くなる、たくましい体つきになる ページの先頭に戻る (6)生活リズムの確立を快食、快眠、快便は、「早寝早起き」の生活リズムから成り立ちます。 ところが、最近、「遅寝遅起き」が原因となり、自立神経のバランスをくずし、 午前中、調子が悪い子どもが増えてきています。
ページの先頭に戻る (7)性教育はあたたかい家庭から体と心がどんどん変わり、親よりも友達を好きになる頃、「思春期の入口に立つ」と言われます。 思春期というのは、一瞬のことではなく、12~3歳の頃から18歳くらいまでを指します。 思春期を迎えた子どもは、私達大人が考えもしないことに興味を持ち、また、思い悩みもします。 特に性に関しては、様々なメディアから情報を仕入れていきます。時には間違った 情報やゆがんだ情報もあり、それをそのまま吸収してしまうことも良くあります。 性を誤って認識してしまう前に、正しい情報を与えることが大切です。 子ども達のそれぞれの体の成長や性意識の個人差が大きいからこそ、生活を共にする家庭での 性教育の必要性があるのです。と言っても、身構えて「性教育を」というのではありません。 暖かい家庭が性教育の最良の場です。両親の生活態度や会話を見聞きしながら、両親が深く信じ合い、 尊敬し合い、愛し合う姿を見て、子ども達は結婚生活の意義や男女の愛を知り、 そして生命の尊さや生きる喜びを学びます。 家族のふれあいの中で、「正しい性=生」を育んでいきたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親は一番身近なモデルです。大人としての生き方や思いやりのある接し方を暮らしの中で さりげなく見せましょう。 ページの先頭に戻る (8)食生活がやる気を左右思春期は、乳幼児期に次いで発育が盛んになり、将来、健康な人生を過ごすためにしっかりとした 体をつくる大切な時期です。特に女子は、母となり、丈夫な子どもを生み育てるための準備の 期間でもあります。 ところが、この時期は、自分達の生活リズムに会わせて、一人で食事をとってしまうことが 多くなるだけでなく、受験へのストレスからくる過食や拒食、美容のための誤った減食や欠食などが 目立ってきます。不規則な食生活を続けていると、病気とまではいかなくても、 イライラしたり、集中力がなくなったり、疲れやすかったりという症状が現れはじめ、 何事にも消極的になりがちになってしまいます。 子ども達が健康で生き生きした学校生活を送るために、まずは、我が家の食生活を見直し、 子ども達の食習慣の自立を支援しましょう。 ページの先頭に戻る (9)朝食ぬきではパワーダウン一日6時間の授業と部活、ともなれば、体にも頭にも相当なエネルギーや栄養が必要になってきます。 それなのに、朝食をとらなかったり、コーヒー一杯とパン一切れ程度の不十分な朝食のまま登校したりすると、 脳や神経系の器官へのエネルギー供給量が低下してしまい、その結果、頭がボーッ、あくびがファ~。 思考力、集中力も共に低下し、午前中の授業にパワーは発揮されません。 豪華な料理でなくとも結構。エネルギー源となる糖質を含むごはんやパン、麺といった主食をしっかりとり、 さらにパワーアップするために必要なビタミンB1を多く含む肉、魚、大豆製品、 卵を上手に組み合わせましょう。 「ビタミン愛」がたっぷりつまった朝ごはんは、きっと子ども達の学校生活をより楽しいものに してくれることでしょう。
◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 朝は、大人も子どもも大忙し。そんな時、冷凍食品などは強力な助っ人。 それだけというのは困りますが、パッケージの栄養成分表示を参考に、短時間でおいしい朝食を 作ってみませんか。 ページの先頭に戻る (10)夜食って、必要なの?熱心に勉強していたら午前様になってしまったということも良くあること。頭を使うことは、 意外とエネルギーを消費するのです。頑張っているんだから何か作ってあげなくちゃと思っても、 ちょっと待ってくださいね。寝る前の食事は、肥満の原因になったり、 安眠を妨害することがあることをご存知ですか? 寝る前に食べ過ぎたり、消化の悪い物を食べたりすると、いざ寝ようと思っても、 胃や腸が消化活動を活発にし続け、そのために寝つかれないことがあります。 その結果として、朝起きられなくなってしまいます。その上、夜食でとったエネルギーが 使われずに蓄積されるために太ったり、コレステロールが増えたりするなど、健康を損ねる原因となります。 反対に空腹すぎると、脳が刺激されて興奮状態になり、これまたなかなか寝つかれず、 朝寝坊となってしまいます。さらに、睡眠不足による食欲不振で、朝食抜きの登校へとつながりかねません。 温めたミルク程度にしたいものです。 夜食作りは、受験勉強の支えにはなりません。子どもの健康を阻害する夜食よりも、 一日の中で最も大切な朝食を作ったり、食べたりできるよう、親も子も朝型の生活に切り替えて いくことをお勧めします。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 太った子でもやせている子でも夜食をとれば、とらない子に比べてコレステロール値が高くなります。 心臓病、糖尿病、高血圧症などの予防は、子ども時代からでも早過ぎるといいうことはありません。 ページの先頭に戻る (11)将来のことを話題にして「進路=受験」と考えられがちですが、それで良いのでしょうか。 「何が何でも高校に入らなければ。合格さえできればどこでもイイ。 それから先は、また、その時になってから考える。」というのでは、学ぶ喜びも楽しみも、 張り合いもないのではありませんか。 勉強は、受験のためにだけあるものではありません。大人になった自分の姿を描いて、 そのためにどんな力を身につければ良いのか、それにはどのような方法があるのかなどと 探っていくことによって、進路選択が具体的になっていきます。 将来を見通し、自分の好きなもの、打ち込みたいものが見えるようになると、 勉強も本物になります。できるだけ早い機会にその方向を見つけ出す手助けをすることが、 大人としての責任でもあります。好きなもの、打ち込みたいものが途中で変わったとしても、 無駄にはなりません。子どもは自分の世界を広げ、深めて成長していきます。 最近、求められている社員像を見ると、実力や人間性を重視するようになり、 学歴主義から実力主義にかわりつつあります。いかに生きるかが問われてきています。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 見栄えの良い職業でも、一歩、内に入ってみると予想を越えた厳しさがあります。 働くことの喜びだけでなく、厳しさや忍耐、コツコツと積み上げることの大切さなどを話題にしたり、 一緒に確かめたりする機会を作ってみませんか。 ページの先頭に戻る (12)勉強できる環境づくりをおいしく朝ごはんを食べていますか。楽しく夕食を味わっていますか。食卓での会話は弾んでいますか。 おいしい食事と楽しい語らい、これは子どもが勉強に精を出すことができる環境作りの譲れない条件です。 胃袋が満たされ、和やかな雰囲気の中で、落ち着いた気分になれば、勉強にも気持ちが向いていくことでしょう。 快食、快眠「快勉(強)」の原動力です。 「胃袋は脳を作る」名言だと思いませんか。 しかし、いくら、食事が大事だからと言っても、夜食はいりません。 夜中の勉強は、とかく身に付かないものです。寝るときにしっかりと寝て、 疲れをとることの方が大切です。今からでも遅くはありません。親子そろって、 早起き組に転向しましょう。親は自分の仕事に、子どもは朝の勉強に精を出しましょう。 親子で新聞を読んで、朝ごはんを食べながら話題にするのもいいですね。親子で活字文化に親しみ、 そこから会話が弾むと自ずと国語の力が身に付き、他の科目の成績を押し上げる原動力となります。 毎日続ければ、気が付いたら、子どもに力が付いていたという具合になるでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 会話がないと嘆くより、話の種となるような共通の話題を見付ける努力をしてみませんか。 口を開けば、小言ばかりでは、そばにいくのさえ嫌になってしまいます。 ページの先頭に戻る (13)再学習のすすめ子どもが小学生の頃は、宿題の手伝いのため、何度ものぞいたりした教科書。 中学生になったとたんに見る機会もほとんどなくなったのではありませんか。 たまに漢字の読み方など聞かれるとちょっとドキドキ。読めなかったら親のプライドに関わるなんて 思ったりしませんか。読めなくたって、大丈夫。「読み方、忘れたナァ。一緒に辞書を引いてみようよ」 「ずいぶん難しい事を習うようになったんだね」と素直に感心してください。 たまには、ちょっと教科書をのぞいてみましょう。自分が中学生だった頃に読んだり、 習ったりしたことを今また改めて目にとめてみると、あの頃とは違った新鮮さでせまってきます。 特に国語の教科書にのっている文学作品など、当時の印象とは違ったものを感じるのではないかと思います。 ひょっとしたら、中学時代にチンプンカンプンだったことが、「何だ、こんなことだったのか」 と頭にすんなりと入ってくるかもしれません。忘却の彼方にあった公式を見れば、 意外に高度な学習をしている子どもに驚きや頼もしさを感じるでしょう。そして、 そのことを話題にしたり、子どもから教えられたり、ともに学んだり…。 子どもは親が一緒に考えてくれたり、親もかなわない難しいことを自分が学んでいることがわかったりすると、 もっと頑張ろうという気持ちになります。親の失敗や苦労話は、子どもの学習意欲をより刺激してくれます。 「勉強をやれ、やれ」と言うよりずっと効果的です。子どもの教科書をちょっと拝借、 再学習をしてみませんか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「努力=良い成績」とならないことも事実です。結果はともかく、努力した過程が大切です。 「今度こそは…」の「こそ」が大切なのです。 ページの先頭に戻る (14)勉強さえしてくれればいいのですか十五の春はうまくいったのに、あとは伸びない人もいます。親の教育熱に支えられて、 勉強オンリー。早く花が咲いたのはいいけれど、そこでおしまい。成績がいいという 自負心があればあるほど、挫折感は大きくなります。 日本の経済は、威勢のいい右上がりから、急カーブで下がり、混乱が起きています。 景気でも勉強でも、ゆるやかに伸びていくのが、幸せです。しかし、それにはそれなりの準備が必要です。 学力を身に付けるには、その基礎となる力を身に付けさせなければなりません。 そのためには、家族の一員としての役割分担をきちんと果たさせるのが近道です。例えば、 休日に家族みんなの洗濯をするというのもいいことです。どれから洗うか仕分けをしたり、 しわにならない干し方を考えたり、取りこむタイミングを考えたり、洗濯一つとっても、 たくさんの工夫を要します。計画、実行、評価という一連の作業が含まれているのです。もちろん、 汚れたものがきれいになって、家族からも喜ばれます。こうして家族の一員としての自覚も育ちます。 これが、実は見えない学力となって蓄積され、学習効果を上げる原動力になるのです。 しかも、「生きる力」もあわせてついていきます。急がば回れというでしょう。 見えない学力をしっかり身に付けさせ、見える学力が花開くのをゆっくり待ちたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子育ての要は、じっくり待つこと。「早く○○しなさい」の口癖は、返上しましょう。 「忍の一字の我慢くらべ」これが実は大事です。 ページの先頭に戻る (15)クラブ活動から学ぶものクラブ活動は、中学生にとって大事な活動の一つです。自分の好きなことを精一杯取り組むことは、 それ自体が意義のあることです。 自分なりの目標を達成しようとする努力の過程は、積極的に自分の人生を切り拓く力を育てるからです。 最近の子ども達は、人とのかかわりを面倒くさがり、インターネットでゲームをしたり動画視聴したり など、一人でいることを好む傾向があると指摘され、 その弊害も様々言われるようになってきました。そのような状況の中、 協調と協力が基盤となるクラブ活動は、望ましい人間関係を学ぶ場としても重要な役割を果たしています。 年齢の異なった集団活動の中では、同学年での励まし合いだけでなく、 先輩と後輩としてのあり方やマナーも学ぶことができます。 また、クラブ活動を通して、「挨拶ができるようになった」とか「我慢強くなった」など、 礼儀正しさや精神的なたくましさが育ってきたという声をよく聞きます。結果として身に付いた 「目に見えない財産」です。 対外試合の結果やコンクールの成績だけでなく、子どもが努力している姿に目を向け、 成長を認め、励ますことのできる親でありたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ つい熱が入ると、自分の体力以上に頑張ってしまいがちな中学生。疲れているなと思ったときには、 無理にでも休養させることが必要です。 ページの先頭に戻る (16)良き友は良きアドバイザー毎日の生活の中で中学生が楽しいと感じることの多くは、友達と話したり、遊んだり、 様々な活動をしたりしながら過ごすことの中にあります。また、いろいろな悩み事や不安が生じた時も、 ほとんどの場合、親しい友達に相談することが多いのです。 中学生にとって、信頼し合える友を得るかどうかは、とても大切なことです。 「親友づくり」が中学校生活の満足度を左右する重要なカギだと言っても過言ではありません。 「親友」は、「親しい友」であると同時に互いに心が通じ合う「心友」であり、 信じ合える「信友」であり、真心をもって付き合わなければならない「真友」でもあります。 親としては、楽しいことや悩み事を共有するだけの関係から、互いに高め合うことができるような 仲に発展するよう、親友づくりを応援したいものです。そのためにも、 子どもの交友関係を知ることは大切です。子どもの友達と顔を合わせた時には気軽に声をかけたり、 挨拶がかわせるようにしたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親自身も子どもが選んだ友達やその家族と親しくお付き合いできるよう、心がけてみませんか。 子どもを通じて、世界がきっと広がるはずです。 ページの先頭に戻る (17)いじめに気付いたときいじめにあった子どもの多くは、誰にも言えず、とても悩んでいます。 早く、誰かが気付き、助けないと、もっと深い苦しみを重ねることになります。 また、いじめている側についても、その行為が相手にどのような影響を与えているかが分からない 場合が多くあります。 子どもは、親にふがいなさを責められることや仕返しを恐れ、いじめにあっていることを話そうとしません。 また、いじめている子どもは、さとられないようにかくします。だから、いじめは、 周囲の者がなかなか気付かないものです。しかし、どんな場合でも子ども自身からは何らかの サインが出ているのです。大人は、それを見逃さないよう、気を付けることが大切です。 しかも繰り返し行われ、次第にエスカレートしていきます。
ページの先頭に戻る (18)地域の一員として生きる子どもは、いつの時代でも、学校で学び、家庭で育まれ、地域社会で鍛えられて 一人前になると言われてきています。その3つのステージはそれぞれ味が違いますが、 どれも不可欠です。 今、青少年に最も欠けているのが地域社会の一員としての体験です。この地域とのかかわりが 郷土への愛着にもつながるものです。国際化社会と言われる今日ですが、故郷を知らず、 故郷を愛さずに、世界への眼だけを開こうとしても、できるわけがありません。 ですから、意図的に地域の活動に我が子をかかわらせたり、隣近所の人たちとのふれあいを すすめたりすることが必要となってきます。 回覧板回しでも、なんでもかまいません。地域の人々と接触する機会を作り、 地域の一員であることを自他ともに認めさせることが大切です。 地域のイベントに参加させることもいいでしょう。できれば、大人が段取りをしたところに 顔を出すというよりは、役割分担をさせながら、地域の活動を担っているのだという 責任を持たせたいものです。地域の人達に認められながら、地域の若者として育つことは、 子どもにとって、大きな支えとなるはずです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親とは会話をしなくても、小さいときから世話になってきた近所のおじさんやおばさんに 話しかけられれば、意外と素直に受け答えをするものです。地域の方々の力は、どんどんお借りしましょう。 ページの先頭に戻る (19)子離れの準備日本では、成人は18歳から。 ところが、18歳になったからといって、独り立ちができるかといえば、そうではないのが現状です。 子どもが自立するためには、親の側にも子どもを自立させる準備が必要です。 「うちの子は、何もできないから心配だ。」「うちの子は、まだ、子どもだから」と言って、 子どもを手放さない親の中には、「我が子が、生きがい」「我が子が、すべて」といった タイプが多くいます。何でも子どものやることを先回りし、子ども中心の生活を作り上げ、 子どもが不自由な思いをしなくてもすむように日夜努力している親も案外多くいます。 しかし、親離れをしようとしている思春期の真っ只中の中学生に乳幼児期と同じような扱いを続けていったら、 子どもの自立は望めません。 多少、危険が伴っても、自分で判断できる中学生時代です。子どもを信頼して、様々な体験をさせ、 責任を持った行動をさせることが大切です。親が手を出したり、口を出したりしたくなるでしょうが、 じっと見守ること。これが、子離れの第一歩です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親自身が、自分の仕事や趣味などで、普段の生活が満ち足りていれば、 子どもの自立を見守るゆとりが出てきます。 ※ 民法改正により、2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わりました。 詳しくは >こちら (政府広報オンライン) ページの先頭に戻る (20)親の出番「家族は情緒的集団で、動物と同じだから、私はボスで押し通した」というある親は、 息子が二十歳の誕生日を迎えた日、「私の子育ては終わった」と宣言し、 子育ては楽しかったと話しておりました。子育て終了宣言を言える親こそ、 出番をわきまえた親ではないでしょうか。 現代は、物も情報も豊富にあり、一見暮らしやすそうではありますが、 大人も子どもも多かれ少なかれストレスを抱えて暮らしているのが現状です。 中学生は、特にも心の揺れの多い時期です。善悪の判断や社会正義にかかわる事柄、 様々な不安や悩みには、親として支えてあげましょう。 我が子と正面から向き合い、将来をしっかり見据えて、毅然とした態度で望むこと。 進路の決定や悪をいさめるなどということは、最も大事な出番です。そんなとき、 オロオロしていては、親失格です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親として活躍するには、普段からの親子のあり方が問われます。 親子のコミュニケーションを大事に、互いを思いやりながら生活するよう、こころがけましょう。 ページの先頭に戻る (21)言うべきときに言える強さを中学生になると、家庭より学校、そして友達との関わりがいっそう強くなり、 第二反抗期ともあいまって親とはしだいに距離を置くようになります。 また、この時期は、理想に燃え、正義感が強まり、親達の現実的な考え方や暮らし方に 反発したりもします。そのため、一緒にいたがらず、話しかけても無視したり、 口ごたえしたりすることが多くあります。しかし、親はそんな時でも感情的にならずに ゆったりと接することが大切です。とは言っても、安易に調子を合わせたり、 妥協して機嫌をとったりはしないことです。 この時期は、グンと行動範囲が広まるし、仲間に影響されて反社会的、非社会的行為に 走る危険もあるので、そんな場合は両親の考えを統一して、毅然とした態度で望むことが大切です。 あからさまな嘘をついたり、人をみくびったり差別したりするようなことがあったら、 一歩も引かない親の姿が重要です。親自身が自分の考えをしっかり持ち、よそではどうであろうと、 「我が家はこの方針で」を通す強い信念が望まれます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 人間として当たり前のことを教えなければ、後々困るのは、我が子です。 口当たりのいいことだけでは、一人前の人間には育ちません。 ページの先頭に戻る |