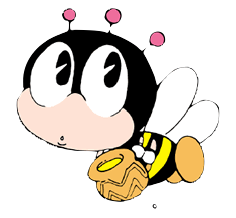

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 小学校中学年編
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
小学校中学年編
|
(1)楽しい家庭 (2)ギャングエイジの心 (3)ギャングエイジの体 (4)ヤングエイジの体 (5)生まれたときのこと (6)命の尊さ (7)運動能力 (8)遊びで体力づくり (9)生活リズム (10)大事な朝食 (11)おやつと食事 (12)楽しい学校 (13)親と教師の関係 (14)読書のすすめ (15)机に向かえば? (16)集団遊び (17)自然体験 (18)地域とともに (19)学級PTA (20)長所と短所 (21)ほめてしかる (22)子どもと向き合う |
(1)楽しい家庭いつも、家族みんなが励まし合い、支え合って暮らしていますか。 「あー、家はいいなあ」と互いにくつろぎ、元気を回復するところが家庭です。 そして家庭は、子育ての学校なのです。家族が尊敬し合い、いつも仲良く過ごしている ことが条件になります。こういう家庭からは非行に走る子は出ないと言われています。 子どもは、毎日、教科書も時間割もない暮らしの中で、知らず知らずのうちにお手本の 両親とじかにふれあい、五感を総動員して人間関係のルールや人としての生き方を身に つけていきます。だから、両親のしつけや人生観が一致していることが大切です。 みなさんいかがでしょう。 昔から「子どもは親に似る」と言われます。「親の言う通りよりも、やる通りの子」が 育ちます。だから、親は「生きた教科書」そのものです。さり気ない日々の暮らしの中で、 気負わず、気長に、家族みんながそれぞれの役割を果たし、共感し合って温かな人間関係を 育んでいきたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 楽しい家庭づくりの特効薬はどこにも売っていません。家庭はつくって与えるものではなく、 家族が創意工夫し合い、「つくり上げていく」ものです。 ページの先頭に戻る (2)ギャングエイジのころの心小学生も中学年になると、「自分で何でもできるぞ」と行動的になってきます。 今まで柔順だった子が、反発したり、強く自己主張したりします。 これは立派な「自我の芽生え」で、あわてる必要はありません。ゆったりとした 気持ちで見つめる心が大切です。また、この時期は急に仲間を求め、友だち付き合いも増え、 集団で行動することも多くなり、「ギャングエイジ」とも呼ばれます。仲間意識が一段と 強まる時期なのです。 友だちも、単に数が増えるだけでなく、異年齢や異性の友だちへと広がる重要な節目でもあり、 さまざまな集団に属する喜びやルールも身に付けていきます。 ただ、判断力はまだまだ甘く、暴走しがちなので、手は離しても目は離せない時期です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ この年齢でポツンと取り残されているような子には注意が必要です。 決して強制してはなりませんが、仲間外れやいじめのターゲットになっているような場合は、 大人の配慮や支援が必要となります。 ページの先頭に戻る (3)ギャングエイジのころの体 ~発達傾向~小学校3年生ごろになると、体の発達に個人差や男女差が見え始めてきます。 今までの子どもの体形から、身長や体重が増え、また筋肉の発達が見られ、 少しずつ大人の体へ近付いてきます。 身長をみると、平均すれば小学校3年生までは男子の方が高く、4年生ぐらいで男女同じぐらいになり、 5年生になると女子の方が高くなっていく傾向があります。中学生になるとまた男子が女子を 追い抜くことから、女子の体の発達・変化は男子に比べて少し早めにスタートするようです。 3年生ごろから女子は体つきにも変化があらわれ、胸が少しずつふくらんだり、 腰まわりがふっくらとし、丸みを帯びた体つきになり、初潮を迎える子もいます。 このような変化の現れる時期は年々低年齢化しています。 成長に個人差や性差がみられるようになると友だちと体を比べたり、感受性が高まるなど 心の変化も出てきます。個人差はあっても体は確実に成長しているのですから、 一人一人の成長を家族がしっかり受け止め、温かく見守ってあげることが大切です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 心と体の成長にアンバランスを生じがちなこの時期の子ども、一人一人の成長を見守り、 悩みを聞いてあげましょう。 ページの先頭に戻る (4)ギャングエイジのころの体~性について~性教育とは何でしょう。とかく「性」だけを独立させて考えがちですが、 基本は生命の尊さや自分とは人間とは何かを学んでいく「生き方教育」 と言われています。 体の発達が早まり、性について興味や関心をもつ時期も低年齢化してきています。 テレビや雑誌などから性に関する情報があふれる現状では、子どもたちが正しい知識を 得る前に興味本位に情報をうのみにしていくことが心配です。 学校では保健や道徳の授業など多方面から性教育をすすめています。 保健の授業は、3年生から始まります。 学習だけでなく集団生活の中でも、望ましい人間関係や心と体を大切にする気持ちを学んでいます。 家庭では、家族が生活の中で信じ合い、尊敬し合い、助け合う姿を見て、 命の大切さや生きる喜びを学んでいくことでしょう。難しく考えず、 学校で学んできたことをきっかけに、あるいは一緒に本を読みながら、 お風呂に入りながら心のことや体のことを子どもと明るく話してみませんか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 何でも話せる親子関係や日常生活そのものが性教育のための最高の環境です。 子どもと一緒に悩み、考えてあげましょう。 ページの先頭に戻る (5)生まれたときのことを教えて「誕生日」、それは大切な”新しい命”が生まれた日です。お子さんに、生まれたときのことを 話したことがありますか。自分がどのように大切に育てられ愛されてきたかを、 心や体が少しずつ大人に近づいてきているこの時期に考えさせたいものです。 お父さんやお母さん、おじいさんやおばあさん、そして家族みんながその命の誕生を 待ちこがれていたことを話してほしいものです。お母さんのお腹の中で大きくなったときのこと、 出産をひかえ大変なお母さんを支えてくれた家族のこと、そして生まれた日のこと、 どんな願いで自分の名前をつけてくれたか。そんな話の中で、きっと家族の中の「自分」を 再確認することでしょう。 そして何人もの命を受け継いだ「新しい命」の重みと喜びを知ることで、命を大切に する気持ちや困ったときにも負けない強い心をもつことができるでしょう。 誕生日とは、自分を生んでくれたお母さんに感謝する日であり、自分の成長を心から喜んで くれる家族にも感謝する日であることに気付くことができたなら、どんなに素晴らしいことでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 自分の誕生までに両親や家族には、さまざまな苦労や喜び、楽しみがあったことを話す中で、 命の大切さにきっと気付いてくれるでしょう。 ページの先頭に戻る (6)命の尊さを感じる心を今の子どもたちは、かけがえのないそれぞれの命を、どれほど実感して生きているでしょう。 いじめなどは、人の命の大切さを身をもって感じる体験の不足などから生じているように思われます。 裏を返すと生きることの素晴らしさを知らないために起きるものかもしれません。 花壇に芽生えたチューリップの上を平然と歩く小学生もいれば、それを見て植物の命が うばわれることに心痛める子もいます。虫を飼ったり、花を育てたりしている子は、 決してチューリップの芽を見逃さないようです。それは、生き物に対する愛情と畏敬の心が 育っているからでしょう。 自分よりも幼い子や障がいを持つ人、老人などのお世話をする体験なども是非させたいものです。 もちろん、生の対極にある死についても考えさせたいものです。 これらのことは、言葉で教え込もうとしてもなかなか身につきません。命あるものとのふれあいが どうしても必要となります。できれば、丸ごと生き物とふれあう経験をさせたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 人の命が他の動植物の命とつながっていることを、実生活と結びつけて実感させたいものです。 ページの先頭に戻る (7)中学年の運動能力中学年は、身長、体重等が急激な伸びを示すとともに、運動機能も発達する時期と言われています。 これらのことは、体力や運動能力の発達にも大いに関連があり、さまざまな運動種目を しっかり学習できるようになります。例えば、運動が上手にできる力や素早く動ける力などが 発達するのもこの頃で、跳び箱の開脚跳びや鉄棒の逆上がりなどいろいろな技に挑戦 できるようになります。 また、さまざまな運動能力が発達するとともに完成期に近づくため、特定の運動種目だけに 取り組むといったことは避けるべきです。多くの運動種目を決して無理のない運動量で 行うのがよいでしょう。中学年における体力づくりは、バランスを重視したものが望ましいと言えそうです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 体力とは、体の運動能力・抵抗力・耐久力などの総合的な力をいいます。つまり、生きていくための源です。 ページの先頭に戻る (8)遊びを通しての体力づくり中学年の頃は体力をつけていくのに非常に大切な時期です。 どのようにして体力をつけていけばよいのでしょうか。実は、 何も特別なことをする必要はないのです。自然の中で、 伸び伸びといろいろな遊びをすることで十分な体力が身につきます。 しかし、最近は屋外で遊ぶことが少なくなったために、子どもたちの体力が低下しています。 生活様式の変化により、子どもたちが体を動かしたり、働いたりする習慣がどんどん減り、 体力が落ちてきているのです。このことに危機感を持つ必要があります。 また、子どもは遊びを通して、スムーズな人間関係づくりを学びます。この感覚こそが、 今、最も必要とされるものなのです。これらのことを考え合わせると、 特に屋外での遊びを意識してすすめる必要があるのではないでしょうか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 長縄とび、石けり、缶けり、木登り、水遊び・・・。 子どもの頃を思い出して、子どもたちに遊びの楽しさを教えてあげましょう。 ページの先頭に戻る (9)大事な生活のリズム私たちの生活の中で、健康生活といえば、「早寝・早起き」ということがよく言われます。 ランプで生活していた時代ならともかく、現代でも本当に「早寝・早起き」は必要なのでしょうか。 それはやはり必要です。 私たちの体のリズムは1日約25時間で進むという報告があります。このことは、 1日に1時間だけ体内リズムが遅れていくということを意味します。その結果、 一月のうち何日かは、日中なのに自分の体にとっては真夜中ということになってしまうのです。 こうなると、日中に活動する能力が落ちてしまいます。そればかりか、 このような状態が大人になっても続きやすくなってしまいます。これらを防ぎ、 体のリズムを整えるためには、乳幼児の頃からの「早寝・早起き」の習慣が大切となります。 もちろん、「早寝・早起き」をするためには、毎日の生活のリズムを整える必要があります。 つまり、食事、家庭学習、遊び、テレビ等の時間設定を計画的に行うことが重要なのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「早寝・早起き」は、健康の秘訣であり、毎日の活動の原動力です。 ページの先頭に戻る (10)大事な朝食最近、朝食をとらないで登校する子どもが増えています。朝食は、1日の生活リズムを形成するために大きな働きをします。そして、1日の活動のためのエネルギー源でもあります。空腹のまま活動すると疲れやすく、体力を消耗したり、体調が崩れたりします。持久力や集中力の低下なども招き、学習意欲もなくなってきます。また、栄養的にもアンバランスになり、特にカルシウムなどの栄養素が不足してきます。そのほか、朝食を抜くことで、間食や夜食の量が多くなり、肥満の原因にもなります。 朝食を抜く理由としては、「食事をとる時間がない」、「食欲がない」などがあげられます。1日の生活リズムを整え、朝食をとり始める30分から1時間前に起床できるように、夜ふかしをさせないことを心がけましょう。 朝食抜きでは、一日、パワーダウンです。 ~朝ごはんは、黄・赤・緑でバランスよく~
◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 朝食に主食(ごはんやパン)をしっかりとることが、1日のエネルギー源を確保することになるのはもちろん、脳の働きを活発にし、精神的にも安定した状態にさせます。 ページの先頭に戻る (11)おやつと食事成長期の子どもにとって、”おやつ”を食べることは、栄養を補給するだけでなく、 心理面でも大きな役割を果たしています。しかし、そのおやつのとり方によっては、 肥満や、むし歯など健康面において様々な悪影響がでてきます。 子どもの好きなおやつに、アイスクリーム、スナック菓子、あめなどの菓子類、 カップめんやから揚げなどの食事に近いもの、炭酸飲料、ジュースなどの飲み物があげられます。 このように口当たりが良く、よくかまなくてものどを通るようなものをとり続けることが、 食事時間に空腹を感じない原因になります。特に夕食後のおやつや夜食は、翌朝の食欲不振につながります。 成長期の間食は、1日の栄養摂取の中で不足しがちなカルシウムや鉄などの 無機質やビタミン類を適切に補う食品や、その量についても理解させることが大事です。 そして、自分でその選択ができるようにすることも必要です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 〇おやつは時間を決めて与えましょう。欠食・夜食はよくありません。 (夜食は、肥満の原因になります。) 〇手作りのおやつは、甘味や塩味の調整ができますし、親子のふれあいにもなります。 たまには親子でおやつを作るのもいいですね。 ○おやつは食事の一部と考え、1日に必要なエネルギー量の10~15%程度にとどめ、 糖質や脂質、塩分のとりすぎに注意しましょう。 ○給食のない日や休日には、牛乳を飲まない子どもが多く、カルシウムの不足がみられます。 おやつに牛乳を飲むことで補うことができます。 ページの先頭に戻る (12)楽しい学校最近、広場や路地で仲間と遊ぶ子どもの姿をほとんど見ることがなくなってしまいました。 今や学校は子どもたちにとって数少ない友だちとの交流の場です。 また、人間として生きるために大事な社会性を学ぶ場でもあります。 お互いの成長をみんなで励まし、喜び合うことで、うれしさが何倍にもなり、 それが子どもの頑張るエネルギーになります。 前にこんな話を聞いたことがあります。縄跳びがとても盛んな学校で、 子どもたちは記録を競い合い、暇をみつけては練習をしていたそうです。 そんなある日、A君という子が難しい技で先生の記録を超え、 まわりのみんなから拍手喝采を浴びました。そのことをきっかけにA君は自信をもって 何事にも挑戦するようになり、成績も飛躍的に伸びたということです。 学校は友だちや先生と集団で過ごす場所ですから、そこにはそれなりのルールがあります。 一人一人がルールを守り、友だちと力を合わせて物事を成し遂げていく中にも、また、 大きな喜びがあります。 子どもの成長を見守る大人としては、学校が子どもにとってかけがえのない 場所であることを心にとめ、そこでの人間関係を大事にするように励ましたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 良い集団が良い人間性を育てます。親は、子どもの友だちを大事にしてあげたいものです。 ページの先頭に戻る (13)親と教師の関係づくり気がねなくどんなことでも親と教師が話し合えたらどんなにいいでしょう。 教師には評価という仕事もあるために、親としては、何か言ったら子どもが不当な扱いを 受けるのではないかと心配な気持ちもあって、先生と向き合うときには、 つい構えてしまうのではないでしょうか。 教師の方でも、一人一人の子どもが能力を発揮できるよう指導に努めてはいても、 まだ十分ではないと思って、申し訳ないという気持ちでいるかも知れません。 子どもの幸せという共通の願いを持ちながら、親も教師も、お互いの気持ちを考え過ぎて 遠慮している場合もあるかもしれません。 困ったことがなくても、普段から機会をとらえて教師に声をかけることをおすすめします。 話してみることで、子どもを見る目が広がり、子どものいろいろな面が見えてきます。 親と教師の良い関係が、親や教師に対する子どもの信頼を深めます。この信頼の深まりが 良い子どもを育てます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 教師と笑顔であいさつを交わし合い、気軽に声をかけ合う関係ができたとき、 子どもの目がもっと輝いてきます。 ページの先頭に戻る (14)読書のすすめテレビからは、以前は本でしか読むことができなかった名作が映像化され、次々に流れてきます。 また、必要な知識や情報もインターネットで世界中からあっという間に手に入れることが できます。でも、テレビもコンピュータも、情報が次々に目の前を通り過ぎて行くので、 子どもたちが自分で想像し、自分の考えを組み立てるゆとりがありません。 読書は、自分の早さで読み、自分の経験を通して考えたり、想像したりするので、 そこにはだれとも異なる「自分の感動」があります。そして、その「自分の感動」は、 自分自身(人格)をつくっていく大事な糧となります。 子どものときにプレゼントにもらった絵本がもとで、トロイの遺跡を発掘した シュリーマンの話はあまりにも有名ですが、一冊の本が人間の一生を左右するというのは、 シュリーマンに限らずよくあることです。 忙しい毎日の暮らしですが、子どもと一緒に本を読んでみましょう。 いつもより会話がはずむことになります。子どもはそのように自分に向き合ってくれる 親の深い愛情を肌で感じ取るのではないでしょうか。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 本を選ぶときの親とのはずむ会話、夢のある絵本や文、未知の世界への誘い…。 一冊の本を巡ってたくさんの楽しさがあります。 ページの先頭に戻る (15)机に向かっていればいいのでしょうか?子どもたちには、机に向かう勉強の他に、生活の中からいろいろなことを学ぶ機会がたくさんあります。 例えば、親と夕食の買い物に出かけると、野菜や魚の名前を見ているうちに漢字を覚えます。 また、りんごを5個買えば、かけ算やおつりの計算が始まります。商品がどこで作られたか、 あるいは、産地はどこかなどを話し合えば、社会科的な見方が身についてきます。 こんな親子のふれあいからでもいい勉強ができます。 生活の中で、ものの見方や考え方を広め、深めていくことは実に見えない学力となって蓄積され、 学習効果をあげる原動力となるのです。この見えない学力が、「生きる力」なのです。 学校の「総合的な学習の時間」では、 知識を教え込む授業ではなく、自ら学び、自ら考える力の育成と学び方や調べ方を身につけることを ねらいとした授業が繰り広げられています。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「総合的な学習の時間」で重視されている内容には、自然体験やボランティア活動、 ものづくりなどの体験的な学習や問題解決的な学習などがあります。各学校では、 それぞれの特色を生かした計画を立て、「生きる力」を育てています。 家庭でも、机の上での学習だけでなく、いろいろな体験をさせるよう試みてください。 ページの先頭に戻る (16)集団遊びを子どもたちへこの時期の子どもは、親から離れて友だちと遊ぶ集団を形成し、 活発に活動する中で様々なことを学びます。 子どもたちは、集団としての遊びの中でお互いに競争したり、対立したり、 役割を分担したりしながら、ルールを守ること、責任をもつこと、助け合うこと、 弱い者をいたわることなどを身につけていきます。人間として、生きていく上で 大切な社会性の基礎が養われていくのです。 家に閉じこもってゲームや マンガにばかり夢中になっている子どもたちに、戸外で仲間と群がって遊ぶ楽しさを教えるには、 どうしたらよいのでしょう。 まず、第一に、遊びを否定的にとらえがちな大人の見方を改めることです。 児童期の遊び体験の不足は、生き生きとした心の発達を妨げ、 精神的未熟児をつくってしまうおそれがあります。子どもの遊びへの意欲をかきたてるような ことを考えていきたいものです。第二に、大切なことは、子どもの遊びの条件を整えることです。 子どもが群れて遊べるような環境や機会を積極的につくり出していくのが、親や地域の大きな努めです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもの社会性を育てるには、まず、親が地域の催し物に参加することです。 そして、子どもたちを地域の活動や子ども会の行事に積極的に参加させましょう。 人は多くの人とふれあえばふれあうほど、社会性が身についてきます。親は子の鏡です。 ページの先頭に戻る (17)たくましい子どもを育てる自然体験子どもは、人や文化とのふれあいとともに、自然の中でのいろいろな体験を通して、 健全な発達をしていきます。 しかし、今、子どもをとりまく環境は大きく変わってきています。遊びについても、 人間形成に大きな影響を与えてきた自然とのかかわり合いが、次第に失われつつあります。 本来、子どもたちは、泥んこになって、無心に虫とりや魚とりに興じ、 木登りや山登りに汗を流します。そうした体験を通して驚きや感動を体験し、 豊かな感性をはぐくむとともに、自然や環境を大事にする心やがまんすることの大切さなどを学びます。 今の子どもにこそ自然体験は、必要ではないでしょうか。 親がしなければならないことは、自然とのふれあいのための仲間、時間、 場所などをつくることに理解を示すことです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 青少年向けの、自然とのふれあいをすすめる様々な催しに参加させることも必要です。 自分の少年期の自然体験を積極的に話して聞かせ、一緒になって行動してみましょう。 ページの先頭に戻る (18)地域とともに子育てを子どもたちは、家庭だけでなく、地域や学校から様々な影響を受けて育ちます。 特にも、地域からは、人間とし生きていくための知恵を、実践を通して教わります。 そこから学んだことがらは、生きていくための大きな支えとなります。 自分の住んでいる地域の素晴らしさやそこに住む人たちに支えられて生きているのだということを 実感させるためにも、地域で行われるさまざまな活動に親子で参加することが大事です。 あなたのお子さんは、大人に混じって、祭りでみこしをかついだり、公園の清掃をしたり、 スポーツ大会に参加したりしたことがありますか。 地域の自治会等では、世代を超えた様々な活動が行われています。中学年のときこそ、 地域活動に参加させるよいチャンスです。いろいろな人たちと交流を深めることで、 地域の子どもとして認められていきます。大人の温かなまなざしの中で成長できることは、 子どもにとっても親にとっても素晴らしいことです。地域の中にとけこんでいけば 「隣は何をする人ぞ」といった感じはなくなります。子育てについての不安や悩みだって 気軽に話し合えるような関係もできてくるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 地域の行事では、大人が手を出し過ぎないようにしましょう。子どもがお客様になってしまっては、 本来育つべき自主性や連帯感が影をひそめ、依頼心ばかりが強くなってしまいます。 ページの先頭に戻る (19)学級PTA活動をさかんに子どものすこやかな成長を図ることを目的としたPTA活動を通して、 親もまた成長していくものです。年に何回かのPTA行事には、積極的に参加しましょう。 また、学級の親同士が話し合う機会をもつこともおすすめします。 学級懇談会に参加して、子どもの学習の様子だけでなく、親の自己紹介や家庭の できごとなどを話して親と先生が親しくなることも立派なPTA活動です。 家庭や学級での子どもたちの様子についてお互いに情報交換をすることは、 子どもの変化を発見する手がかりになるかもしれません。運動会、 学習発表会等での親の目から見た子どもたちの良さを話題にすることは、 親同士の交流を深めることになるでしょう。そして、わが子の友だちをさらに 理解することにもつながります。学級のどの子の良さも話題にできる学級懇談会を やってみませんか。親の失敗を語ることができればもっと親密になれるでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ オールマイティな人はいません。同じ悩みを持つ人や失敗の経験がある人に親近感を覚えるものです。 親同士で失敗を語ることは恥ではありません。むしろお互いにより近づくことになります。 ページの先頭に戻る (20)長所と短所は裏表~わが子の持ち味を~わが子の長所と短所をあげてみてください。どれくらい長所をあげられましたか。 残念ながら短所の方が多かったのではありませんか。 ためしに短所を長所に翻訳してみませんか。落ち着きのない子、 勉強も作業もマイペースで行う子等々、どれもイライラしますね。 でも、元気あふれている子、何にでも興味がある子、納得しながらやっていく子、 慎重な子のように翻訳してみるのです。短所を責めて文句を言っても親の思うようには変わりません。 かえって子どもを落ちこませることになります。「時間をかけて丁寧にしたいんだね」、 「詳しく知りたいんだね」と前向きに子どもに応えてあげましょう。そして、 「~すればもっといいかもね」と向上のヒントを必ず添えるようにしてみましょう。 短所を指摘されても、どうすればいいのか子どもは迷っているのです。 どんな小さなことでも良さをみつけ、ほめることで、子どもは自信をつけます。 個性は長所も短所も含めてのものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 個性の尊重とは、子どもを自由にさせ甘やかすことではありません。 自分の良いところに気付かせ、正しく伸ばしていけるように導いていくことです。 ページの先頭に戻る (21)しっかりほめて、ピリッと叱るほめ方や叱り方の方法ではなく、子どもの心を育てることに目を向けてみませんか。 自分でも納得できることを本気でほめられたり叱られたりするのは、 本当は気持ちの良いものです。小さいことでも子ども自身が満ち足りているときは 惜しみなくほめましょう。ほめるということは、認めるということです。 おだてるのとは違います。親が本当にうれしい気持ちになれば、子どもはもっとうれしくなります。 叱ることを恐れてはいませんか。何がいけないのかどうしていけないのかをはっきりさせて 叱ることは大事なことです。そのときの感情や思惑で叱るのは、反感のみが残ります。 ほめても叱っても、そのあと、何秒かの目線を送ってください。無言の愛情あるまなざしは、 子どもの心を安らかにします。 命にかかわることや、人の道に外れるようなことは、もちろん厳しい目で叱らなくてはなりません。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 叱るときは短い言葉でピリッと。くどくどと、あれもこれも言わない。 子どもは何を言われたか忘れてしまっています。 ページの先頭に戻る (22)子どもと親の向かい合い子どもが何か話しかけてきたとき、あなたは子どもの目を見て聞いていますか。 仕事をしながら耳や背中だけで聞いてはいませんか。 この時期の子どもには目線がとても大切です。そんなに長い時間ではないのです。 子どもの目をのぞきこんで聞いてください。こうした日常の積み重ねが、 本気で親の心を伝えるときの基礎になります。 子どもは気持ちを表す適当な言葉をみつけられなくて、黙ってしまうかもしれません。 しかし、ちょっと待って言い分をゆっくり聞いてあげましょう。その上で、 人間として、集団の一人として守らなければならない大切なことを、 きちんと話してあげましょう。子どもは話を真剣に聞いてもらい、 一人の人間として尊重されていると感じると、親の話を素直に受け入れることができるはずです。 大事なことは妥協することなく、子どもの目をのぞきこんで本気で話すようになりたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 聞き上手な親は子どもが言い終わるまで言葉をさしはさまず、うなずいて聞きます。 子どもの言葉を先取りして代わって言ったりしません。 ページの先頭に戻る |