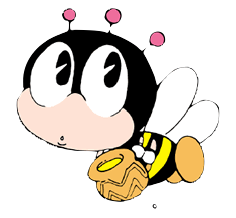

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 乳幼児期の子育てのために
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
乳幼児期の子育てのために
|
(1)新米パパ・ママへ (2)あんよは上手 (3)おむつのはずし方 (4)赤ちゃんのことば (5)離乳食へ (6)あかちゃんの目 (7)子どもの病気 (8)身近な危険 (9)いっしょに遊ぶ (10)遊びの中で育つ (11)読みきかせと語り (12)心の基地 (13)ほめ上手叱り上手 (14)下の子の誕生 (15)共働きの子育て (16)子どもに寄り添う (17)お父さんの出番 (18)これからの子育て (19)再びパパママへ |
(1)新米パパ・ママへみなさんは、わが子への基本的なしつけは何であり、その際の親の役割は何かを、 はっきり知りたいという願いでいっぱいでしょう。 家庭が明るく、なごやかな雰囲気につつまれ、そして親の愛情と知識と技が備わっていれば、 子どもは安心して生活ができ、望ましい成長が期待できるのです。 あなたなりにそれに向かって努力してみましょう。 子どもは、いつでも一緒にいる親の後ろ姿や横顔を見て育っています。 このことを心にしっかりと止めて、親も子も共に成長していってほしいものです。 乳幼児期は、一生のうちで最も成長の著しい時期です。 まずは、心身の発達状況を良く知ることです。 ページの先頭に戻る (2)あんよは上手『這えば立て、立てば歩めの親心』 子どもが一人立ちし、歩き始めるともう赤ちゃんではありません。 歩き始めた頃の子どもは、一歩一歩力を入れ、自分の足がふみしめる大地の感触を確かめるように歩きます。 そして一歩歩いては転び、二歩歩いては転びながら、一人で起き上がり、また歩き始めます。 親はこんな子どもに「さあ立ってごらん、そう立てたね。」と励まし声援を送ります。 ここには、子どもの成長・発達の姿が見事に表現されています。 子どもは一歩一歩ゆっくりと着実に成長発達していきます。しかし、転ぶことも度々です。 でも、親はすぐ手を出さずに子どもの成長をじっと見守ってあげましょう。 ページの先頭に戻る (3)おむつのはずし方「おしっこたくさん出てよかったね。」「うんちいっぱいしてよかったね。」 「ほうら、いい気持ちでしょう。」と声をかけられながら、おむつをとりかえてもらったら、 とても気持ちよさそうです。優しい言葉をたくさんかけてあげながら、こまめにとりかえてあげましょう。 心地よさを感じてくれたらしめたものです。おむつが汚れていない時に便器に座らせて うまく排尿できたら誉めてあげましょう。何度も繰り返すうちに、便器での排泄にも慣れていくでしょう おむつやパンツを汚したことを怒らず優しく声がけしながら励ましてあげましょう。 ページの先頭に戻る (4)赤ちゃんのことば「マママ・・・ブーブー・・」と発声練習をしていた赤ちゃんが「ママ」とか「ウマウマ」 とか意味のある言葉を話し出した時、親はとてもうれしいものです。 子どもが言葉で自分の気持ちを伝えることができるようになると、子どもの世界はとても豊かになります。 でもこの時期の子どもの言葉は気持ちを十分伝えるには不足しています。 親は子どもの言いたい気持ちをゆっくり聞いてあげて、正しい言葉で返してあげましょう。 かわいいからと言って、親まで赤ちゃん言葉を使ったり、あるいは無理に言葉を教えたりしようとせずに、 親は大人の言葉で子どもの言いたい気持ちを補ってあげましょう。 子どもにたくさんお話しすることが子どもの言葉の発達を促します。 ページの先頭に戻る (5)離乳食へ「いつ頃から離乳を始めればいいんですか?」と、よく質問を受けます。 昔から「お食い初め」と言って生後100日前後が、おっぱいだけでなく、 子どもに合った食べ物を与え始めるしきたりがあります。これは、今も昔も変わりありません。
ママに好き嫌いがあると、子どもに与える物に片寄りが出ます。ママやパパの好き嫌いを無くしましょう。 大人の味つけよりは薄味にすることも必要です。 ページの先頭に戻る (6)赤ちゃんの目赤ちゃんはおっぱいを飲んで寝ているだけのように思われますが、 実はもう十分周りの状況に反応する力をもっているのです。 あやしたり抱いたりしてくれるママとの肌のふれあいを通して愛情を感じとって快い喜びを味わいます。 生後2か月頃からは、ママを見てほほえみかけるようになります。 7~8か月頃には「人見知り」が始まります。 これは赤ちゃんの中にママのイメージが深く刻み込まれたことを意味します。 一緒に過ごす親が思いやり、幸せな気持ちで生活することで赤ちゃんの情緒は安定し、 親子の絆が育っていきます。 ページの先頭に戻る (7)子どもの病気赤ちゃんは、ママのお腹(羊水という水の中)で成長してきました。 生まれると同時に、今度は空気を吸って酸素を取らなくてはなりません。栄養も、 移動する力も、細菌やウイルスなどへの抵抗力も、自分でつけなければなりません。 その子ども達に色々な病気、障がいがおこることがあります。子どもを守り育てる ママやパパ、みんなを応援するのが、予防接種や育児相談、 そして、発育や発達の節目ごとに行われる健診です。大いに利用したいものです。 子どもが重い病気をもっていたとしても、親が一人で苦しまないよう、 親しい友達やかかりつけ医の先生にも、ふだんから子どもを知っておいてもらいましょう。 ページの先頭に戻る (8)身近な危険赤ちゃんの周りには危険な物が沢山あります。 赤ちゃんは、何が危ない物なのかわかりません。赤ちゃんの救急の第一は火傷です。 ポットを倒して火傷をさせる例が多くあります。 幼稚園に入るまでは、押せばすぐ出る式のポットは身近な場所に置かないようにしましょう。 その他の危ない物はホチキスの針。 赤ちゃんは良く小さな物を拾います。ビニールやサランラップ で窒息した例があります。字が読めないので、 酸化防止剤や乾燥剤をすぐ口に入れて呑み込んでしまいます。 ボールペンのキャップ。これが気管につまりレントゲン写真でも解らなかった例があります。 腹這いになって、赤ちゃんの目線で周りを見てみましょう。 ページの先頭に戻る (9)いっしょに遊ぶもっとも信頼しているママの歌は、楽しんで聞きます。歌やリズムに合わせて、 手や体を動かしてあげましょう。 ~ポイント~ ○親子で向かい合って足を伸ばして座り、手をつないで、 身近な歌に合わせて体の動きを楽しませてあげましょう。 ○ママが歌を歌いながらの絵かき歌は、子どもがとても喜びます。 また、ママの口の開きを見て、子どもはすぐに歌を覚えます。いろいろな絵を描いてみましょう。 ○歌に合わせての手遊びも楽しいものです。パパ、ママなりにいろいろ工夫して、 子どもと一緒にやってみましょう。 ページの先頭に戻る (10)遊びの中で育つ『遊びをせむとや生まれけん・・・』 遊びをするために生まれてきたのかしら、子どもというものは。ほんとにまあ、良く遊ぶこと。 まったくあきれてしまいますよ。 千年も昔の平安時代のはやり歌です。 こまったものだと思いながらも、子どもたちが元気良く遊んでいるのを見ていると、 大人の自分も楽しくなって、つい心がはずんでしまう。・・・という歌です。 子どもは遊びによってたくましく育ち、生きる知恵を身につけていきます。 生まれつきそなわった素質も、遊びを通して芽生え、伸びていきます。 正しく伸びるための[しつけ]はもちろん必要ですが、パパ、ママも、 できるだけ子どもと一緒に遊びましょう。 ページの先頭に戻る (11)読みきかせと語り~お話、大好き~「さあ読んで聞かせるからね。」と絵本の表紙を開く時、あなたは立派な主演俳優です。 「朗読なんてしたことがないし・・・」なんて恥ずかしがることはありません。 観客はあなた自身の子どもなんですから。 「むかーし、むかし、あったとさ。」と昔話を語ってくれたおばあさんたちも、 特に語り方が上手だったわけではありません。でも、子どもたちは、胸をときめかせて聞き入り、 一生その昔話を忘れませんでした。覚えていたのは、物語そのものよりも、語り手の声と表情と、 伝わってくる語り手の気持ちでした。 子どもに自分の思いを伝えよう、その気持ちをたっぷり込めて、さあ、語り始めましょう。 ページの先頭に戻る (12)心の基地3歳頃になると子どもの活動範囲は家庭から外の世界へと広がり、親のもとを離れて、 遊びに出かけていくようになります。けれども、子どもの立ち向かっていく未知の世界は、 魅力的であると同時に不安もたくさんあるのです。ですから、少しでも不安になったりすると、 すぐに親の所にもどり、気持ちが満たされるとまた出かけて行くということを繰り返します。 そこで、この時期の子どもにとっての親は、いつでも安心して戻れる距離と場所にいて、 その時々の子どもの気持ちを受けとめてあげることが必要です。 「子どもの安全基地」としての役割を求められるのです。 ページの先頭に戻る (13)ほめ上手、叱り上手 ~あなたの子育ては「叱る」ことが多くなっていませんか?~①「叱る」ことが多く厳しすぎるしつけは、子どもの自信をなくし、おどおどした裏表のある、 「うそ」をつく子どもに育ちがちと言われています。 <「叱り上手」は「ほめ上手」にほかなりません> 腹をたてて叱ったときは、効果がなく親の負けです。 叱り上手は、子どもの目線まで身をかがめ、 子どもを抱っこして言い含める、教え、さとしながら子どもの長所を見つけてほめ、 「いい子ね。」と言ってあげることです。 <可愛くば二つ叱って三つほめ五つ教えてよき人にせよ(道歌)> ほめることを見つけ、ほめることを多くすることが子どもの「やる気」を引き出し、 自然に「叱る」ことが少なくなる子育てにつながるわけです。 ②子どもと目と目を合わせて叱る親 叱る時には身をかがめ、子どもと目線を合わせ、子どもを抱きかかえ、ゆっくり話をしてあげます。 「○○ちゃんは、こんないいところがあるんだよ、いい子ね。」と 子どもの長所を見つけ出し気づかせ励ましてあげます。親が立ったまま子どもを見おろす形で叱ったり、 子どもから遠く離れて大声で怒鳴ったりするような叱り方は子どもに反感をもたれるだけのようです。 ③「3つのふれあい」を大切にする 「肌のふれあい」、「笑顔のふれあい」、「言葉のふれあい」 幼児期の子育てには、この3つのふれあいが大切です。ほめる、叱る、言葉のふれあいだけでなく、 肌や笑顔のふれあいと一緒であることを実行するよう心がけてみましょう。 ページの先頭に戻る (14)下の子の誕生大きくなったママのお腹を見ながら、「赤ちゃんいつ生まれるの、女の子がいいな。」 などと言っていたのに、いざ下の子が生まれて、真っ赤な顔で「オギャーオギャー」と泣き、 ママの注意がすっかりそちらに向いてしまうと、上の子どもは戸惑ってしまいます。 「こんなことじゃなかった・・・」と淋しい気持ちから、今まで一人でスプーンで食事をしていたのに 「食べさせて。」とねだったり、「お母さんと寝る。」と割り込んできたり、 下の子へいじわるしたりすることが見られることもあります。 短い時間でもいいから上の子どもを抱いてあげて、寂しい気持ちや、嫉妬心を理解してあげ、 親の愛情が上の子どもにも向けられていることを教えてあげてください。 ページの先頭に戻る (15)共働きの子育て最近では、共働きの家庭が多くなってきました。 おばあちゃんが面倒を見てくださる、保育所に預けるなど日中の保育はいろいろでしょう。 いずれにせよ産休明け、あるいは育児休暇明けに他の人に子どもの保育を委ねる時は、 「ならし保育」が必要です。子どもは、保育者が変わると緊張します。 少しずつ慣らしていくことが大事です。そしてママは、 帰宅したら短時間でも、十分に子どもの相手をしてあげましょう。そのためにはパパにも家事、 育児を分担してもらうことが必要でしょう。 育児を他の人にお願いする時は、いろいろな面で連絡を密にしておかなければなりません。 特に病気の時の対応について日頃から連絡し合っておくことを忘れないようにしましょう。 ページの先頭に戻る (16)子どもに寄り添う子どもが自立し始める幼児期には、直接手をかけることを減らして子どもに任せていくことを 多くしていかなくてはなりません。けれども、だからこそ、目も心もしっかりと子どもに向けて、 今何が必要な手助けなのかを見極めて相手をすることが大切です。 なんでも自分でやりたがるこの時期「勝手にやりなさい。」と放っておくのではなく、 見守り、励まし、認めて自分でやってできたという満足感を味わわせましょう。 知りたがり屋で「これなあに?」と次々たずねるのも、 「反抗期」と呼ばれる強い自己主張が見られるのも、この時期。子どもの気持ちを探り、 くみとり、ていねいに応じながら親子のかかわりを深めていきましょう。 ページの先頭に戻る (17)パパや家族の出番子どもの毎日は、新しい時間の連続です。目にするもの、体にふれるもの、すべてが新鮮です。 その刺激を受けて子どもはいきいきと反応し、成長していきます。 ママのふところで始まった子どもの人生は、育つにつれてもっと広い世界へとはばたき始める、 その第一歩がパパや家族とのふれあいです。パパや家族の感触や言葉や行動が、 子どもの世界を大きく押し広げていきます。 さらにお友達や近所の人たちとのふれあいを通じて、子どもは社会に適合する力を身につけていきます。 近所の公園や海や山、森などの様々な舞台が子どもを待っています。 ページの先頭に戻る (18)これからの子育て ~視野を広げて~様々な人やニュースが激しく行き来しています。 今や、地球が一つの住み家のようになってきているように見えます。 アンデルセン、イソップ、ファーブルなどのお話の世界。スパゲッティ、 バナナ、オレンジ、エビやおそばなどの食べ物も。 紙、石油、服、おもちゃなど身のまわりのどんなものを見ても世界中の国の話が出来ます。 外国語を教えることも大切ですが、子ども達が自分の主張をしっかり表現でき、 等しく相手を理解する力と心を養いましょう。外国の話を聞くのは楽しいものです。 そして自分の生まれ育ったふるさとを語ることができるのは、もっと楽しいことです。 21世紀には本当に豊かな日本の国を担える子ども達に育ってほしいものですね。 ページの先頭に戻る (19)再びパパママへ体調をこわしたり、わずらわしい人間関係にまきこまれた時など、子どもの寝顔を見てふっと心がなごみ、 晴れ晴れとすることがありますね。かと思うと、ちょっとしたことで、頭ごなしに子どもをどやしつけたり、 時にはピシャッと手を出してしまったり・・・ 遠い昔、自分の両親にも、やっぱり同じようなことがあったにちがいありません。 思い出すと、両親がたまらなく懐かしくなりますね。 一から十までそっくり同じではないけれど、人間はずいぶん似たような人生をくり返すんですね。 この子もやがて親になった時、やっぱり同じようにして子どもを育てるのでしょう。いとおしくなりますね。 ページの先頭に戻る |