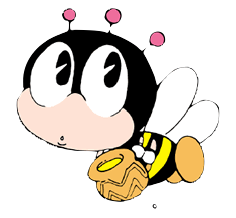

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 小学校高学年編
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
小学校高学年編
|
(1)変わる社会 (2)高学年の心理 (3)反抗期を考える (4)身体と心の変化 (5)身体の発達 (6)生活リズム (7)家庭の性教育 (8)食生活で意欲を (9)おやつの与え方 (10)大事な朝食 (11)手足に力を (12)読書のすすめ (13)家庭学習 (14)集団遊び (15)必要な失敗体験 (16)親子でアウトドア (17)地域で子育て (18)生活習慣 (19)わが子のもち味 (20)親のタイプ (21)ほめて叱る |
(1)変わる社会、変わらぬ家庭車もあります。テレビも冷蔵庫もずいぶん大きくなりました。 男の子のファッションもカラフルになってきました。世の中は、ずいぶんと変わりました。 子どもの世界も様変わりしました。大きい子から小さい子まで群がって遊ぶ姿は、 地域では見られなくなり、ゲームやスマホに熱中する子、 塾通いで忙しい子が多くなってきました。 家の中ではどうでしょう。親も仕事で忙しいようです。 おじいさんやおばあさんがいない家庭も増えてきました。家族が少なくなった上に、 家族全員がそろう時間も少なくなってきました。 でも、親にとって子どもは何にもまさる宝であり、子どもにとって、 この世で一番好きなのは親なのです。これは、 今も昔も少しも変わりません。世の中が変わった、家庭も変わったと一口に言いますが、 世の中は変わっても、「良い家庭」と言われるものは、変わるものではありません。 仕事にかこつけて、家を空けすぎてはいませんか。 忙しいからといって、子どもにあたりちらしてはいませんか。 孫の前で親達のいやみを言っていませんか。大人達は、自分の行動を振り返ってみましょう。 思いやりの気持ちをもち、共に過ごす時間をつくり、お互いをわかりあおうとする心で 相手と接するならば、家族の心は一つにまとまります。それが、今も昔も変わらぬ 「良い家庭」といえるのではないでしょうか。 笑顔と温かい声がけが家庭の心をつなぎます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 食卓を囲んで、1日のできごとを話し合ってみませんか。思いだけでは、なかなかコミュニケーションはとれません。まずは、ちっちゃな会話から始めてみませんか。 ページの先頭に戻る (2)高学年の子どもの心理小学生の年代の子どもは、乳幼児や中学生に比べ、身体の発達が比較的穏やかで、 心の動きも安定しています。しかし、最近、不登校やいじめ、自殺、非行など、 小学生にかかわる様々な問題も増えるに従い、この時期の子どもの心理的な発達に ついても関心がもたれるようになってきました。 高学年になると、学校での勉強も難しくなり、不得意教科が出てくることもあります。 進度についていけなかったり、学習内容が理解できなかったりして、劣等感をもつように なったりもします。幼い頃には感じなかった様々な感情も生まれてきます。 このような心の動きを親に対して素直に打ち明けなくなるのも、この時期の特徴です。 また、交友関係が広がってくるので、家族よりも仲間同士のふれあいを大切にするように なっいきます。親に対して秘密の世界も大きくなり、その中に入り込まれたくない という気持ちも出てきます。 今まで何でも話していた子どもが、急によそよそしくなったり、親と話しもしなくなったりするので 親は困惑しますが、この時期はまさに親からの自立の時期、友人の中で自分を見つめ直す時期と考え、 今までよりも少し離れて子どもの成長を見守りたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 体は大きくなっても、まだまだ子どもです。自立したいと思う気持ちと甘えたい気持ちが 混在しています。そこを理解してあげたいものです。 ページの先頭に戻る (3)反抗期を考える大人の体に変わっていくこの時期には、身体的にも情緒的にも非常に不安定です。 この時期には、内から湧き出す衝動をコントロールしながら、正しい判断や責任ある 行動ができるような心を育てていかなければなりません。 ところが、気持ちの準備が整っていないところに生理が訪れたり、今まで経験したことの ない性衝動につき動かされたりと、子ども達は大きな不安を経験します。そこで、 今までおとなしかった子どもが急に暴力的になったり、口をきかなくなったりするので、 困惑してしまう親もいます。 このような現象は、第二反抗期と呼ばれてきました。この時期を乗り越えるには、 子ども達の反抗をしっかりと受けとめる存在が必要です。そこでのやりとりの中で 子ども達の自我も成長していきます。ところが最近、誰にどのように反抗していけば よいのかわからないまま、いらつく子ども達が増えてきています。いらいらした気持ちがつのり、 対象や目的のはっきりしないいじめや暴力という形で内にたまった感情を発散する子ども達も 見られるようになってきました。とかく親達はおよびごしになりがちですが、 こうした子ども達から逃げないで、子どもの気持ちを受けとめてやることが大切です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ やって良いこと、悪いことが、親の責任ではっきり示すことが大切です。 ものわかりが良いふりをして、教えなければならないことをうやむやにするのは、 子どものためになりません。 ページの先頭に戻る (4)身体に表れる心の変化不登校気味の子どもが、朝「お腹が痛い」とか「頭が痛い」と言って、 起きようとしないことがあります。そんな時、「嘘をついているんでしょう。 また、仮病ばかり使って」と、腹を立ててはいませんか。実は、嘘をついているのではなく、 本当にお腹や頭が痛くなっている場合もあるのです。 「学校に行きたくてもいけない」という心の状態が身体にうつしだされ、 痛みとなってあらわれたのです。 乳幼児は、心と身体が密接に関係しているので、わずかのストレスや欲求不満で熱を出したり、 下痢をしたりします。ところが、小学校も高学年になると心身の機能が分化し、 欲求や行動をコントロールする力も強くなってくるので、乳幼児のように直接身体に 影響を及ぼすことは少なくなります。しかし、最近、この時期の子ども達の中にも 様々な欲求を抑えることができず、不満やストレスをいろいろな形で外にあらわすように なってきました。最近は、大人にもストレスを身体の症状として現わす「心身症」が増えてきています。 「気持ちを聞いてあげる」ことが大切ですが、気持ちを伝えられない子ども達の 「身体から発せられる言葉」を受けとめることはもっと大事です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 疑いの目で見ると、すべてが悪く見えてきます。温かく優しいまなざしで 子どもを見つめることができるようにしたいものです。 ページの先頭に戻る (5)身体の発達の傾向体の発達には、男女差や個人差があります。この差を教えることで、子ども達は、 自分の成長や変化に不安をもたなくなります。成長したことへの喜びや、 将来への期待を親子で話し合える雰囲気は家庭でつくっていきたいものの一つです。 また、体は大人になる準備が始まります。大きく変化が現れ、 子どもは不安を感じたりしがちです。そんな時こそ、親がさりげなく 子どもに話しかけることが大切です。 【発達における男女差】 小学校高学年の頃は、一般的に女子の発育の方が早いといえます。 身長や体重の平均値で見ると、男子より女子の方が上回っています。 【発達における個人差】 小学校高学年の頃は、発達が著しい時期ですが、一人ひとりの発達のしかたにも かなり違いがあります。早く大きくなる人、ゆるやかに大きくなる人、 後から急に大きくなる人など個人によってかなり差があります。 【大人への体の変化】 個人によって差があります。女の子は皮下脂肪がつき、ふっくら丸みを帯びた体つきになります。また、卵巣が発達し、月経が始まります。男の子は筋肉が発達して、がっしりした体つきになってきます。また、精巣が発達し、射精が始まる子もいます。これらはホルモンの働きによるものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ブラジャーを身につける目安は、ある程度乳首が形づくられてからです。 正しい下着の付け方を教えることが大切です。 ページの先頭に戻る (6)生活リズムの確立を「早寝早起き」は、一日の生活リズムの基本となります。生活リズムが整えば、 さわやかに目が覚め、朝食もしっかりとることができます。「眠る・起きる」は 健康な生活リズムづくりの第一歩です。 -生活リズムがくずれるとどうなるの?- ①自分で起きることができなくなります。 誰にも起こされないで自分で起きることは、一日の活動の始まりとしてとても 大切なことです。十分な睡眠をとっていれば、自然に目が覚めるはずです。 ②朝食をとらなくなります。 朝、起きることができなければ、食べる時間も取れず、朝食抜きで登校することになります。 それが繰り返されることにより、朝食に対する感覚が麻痺し、食欲を感じなくなります。 ③不規則な排便になります。 朝食をとらないから、腸に運動刺激が伝わりにくく、便秘になりやすくなります。 ④頭痛、めまい、腹痛、気持ちが悪いなどの症状があらわれます。 自律神経のバランスがくずれて、体にいろいろな症状が現れてきます。 ⑤がんばる気持ちがなくなります。 寝不足だと集中力がなくなり、がんばれなくなります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 小学校高学年の睡眠時間は、9~10時間がひとつの目安ですが、個人差があります。 多少短くてもすっきりさわやかに起きることができれば、子どもにとって「最も適した睡眠時間」と いうことになります。 ページの先頭に戻る (7)性教育は家庭から小学校高学年は、思春期を迎える時期で、心身ともに大きな変化が見えはじめます。 性に対する意識が一層高まる時期で、興味も持ちます。ところが、 親は性に関する話を子どもにはしにくいもので、子ども達は様々なメディアから情報を 仕入れていきます。ときには、間違った情報やゆがんだ情報もあります。暴力や差別、 性への蔑視、興味本位の取り上げ方の情報のみにさらされた子ども達は、それが正しく、 当たり前だと思ってしまうでしょう。正しい知識を教えることと正しい情報の選択の仕方は 家庭でもふれていかなければなりません。 体の変化が始まる時期だからこそ、成長することの喜びを素直に感じさせるようにさせたいものです。 大人の体つきのようになっていくことへの驚きや嫌悪感、友達との比較による劣等感は、 大なり小なりどの子どもも感じることです。その時に、さりげなくアドバイスできるような 準備をしておきたいものです。また、男の子には、射精(精通)、女の子には月経(初潮)と いう大人への準備も始まることも話しておきたいことがらです。 小学校高学年は異性への関心も高まる時期なので、男女がお互いを認め合い、 思いやる心を育てることが大切です。人に対していやがることや傷つくことを言わないとか、 人間らしく生きることについても家庭でしっかり教えていきたいものです。 性教育をする上でのベースとなります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもの質問にどう答えたらよいか迷ったときは、ごまかしたりしないことが大切です。 「あなたはどう思っているの?」「わからないので調べてからね」と話すことから始めましょう。 ページの先頭に戻る (8)意欲に響く食生活小学校の高学年期は、体が急に成長する時期です。特に女子は成人と同じ位まで大きく なる子もいます。立派な体を作るためには、必ず摂らなくてはいけない栄養素や食事の量もあります。 空腹を満たすだけの食事ではなく、食事の量や食品の組み合わせ方を見直していくことが大切です。 このごろは、子どもが一人で食事をとるという光景も珍しくはなくなりましたが、 一人の食事は栄養のバランスを欠くだけでなく、豊かな心を養う上でも悪影響を及ぼすことがあります。 一日に一回は、家族で食卓を囲み、楽しい会話をおかずにして食事をとるようにしたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 夜、遅い夕食は考えものです。寝る時間も考えながら、消化吸収の良いものを 食べさせるようにしましょう。食べてすぐに寝るのは、肥満の原因になります。 ページの先頭に戻る (9)上手なおやつのあたえ方スナック菓子、クッキー、せんべい、菓子パン、ケーキ、果物…、 これらは小学生が良く食べるおやつです。このごろの傾向では市販のものが主流であり、 手づくりおやつが上位にランクされるのは難しいようです。 おやつには、三度の食事でとれなかった栄養を補うことと、心を潤すという大切な役割があります。 しかし、小学校の高学年ともなれば、一回あたりの食事量も増えてきますので、 基本的には三度の食事で十分に一日の栄養をとることができるようになり、 おやつはあまり必要なくなってきます。 疲れた体と心の元気回復のためには、必要なおやつであっても、エネルギー過剰にならないよう 「甘さ半分」の思いやりをしてあげることが大切です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ お店でお菓子をいっしょに選びながら、食べる量を教えることも、上手なおやつの与え方になります。 ページの先頭に戻る (10)朝食抜きでは頭も体も動かない元気に走ったり、楽しく歌ったり、難しい計算をしたり、漢字を覚えたりするためには、 体の中の筋肉や脳にエネルギーがしっかりつまっていなければなりません。 そのエネルギーの元になるのが、ごはん、パン、麺、芋といった、私たちが毎日食べる 主食に多く含まれる炭水化物です。そして、もっと力を発揮するためには、肉、魚、大豆製品、 卵などに多く含まれるビタミンB1が必要です。 朝、時間がないからといって、何も食べずに登校すると、エネルギー不足で勉強にも 遊びにも十分なパワーを出しきれません。愛情がたっぷりつまった朝ごはんは、 きっと子ども達の学校生活を楽しいものにしてくれることでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ どんなに素晴らしい朝ごはんでも、体に入らなければエネルギーにはなりません。 早起きをさせ、食べる時間を確保しましょう。 ページの先頭に戻る (11)手足に力を「塾通いは中学校からでは遅いそうよ」「特に英語はね」こんな会話が聞こえてきます。 まわりがみんな塾通いをしていると、自分の子どもだけが落ちこぼれるのではないかと焦ってしまう。 そんな心境になりがちです。でも、早く始めた方がうまくいくのでしょうか。 就学前から勉強を強いられ、小学校のうちに花は開いたけれども、15の春には泣いたという例は 良く聞きます。 小学校は、基礎体力、基礎学力をつける大事な時期です。言ってみれば、肥料を蓄える時期なのです。 それもすぐ効き目が現れるような化学肥料ではだめです。後でじんわりと効いてくるような 有機肥料タイプがいいのです。 学校では勉強を。家庭では体を動かし、手足を使うことを積極的にさせましょう。十分遊ばせ、 家の仕事をしっかりさせることは、教科の学習と同じように大切です。子どもは体を動かし、 手足を使うことを通して、上手に早く仕上げようといろいろ工夫もします。自分でできた喜びを味わうことで、 後に学習の効果をあげる原動力となっていくのです。 足腰を鍛え、手足に知恵をつける。これが見えない学力なのです。この力が肥やしとなって、 来るべき時期に見える学力となって花が開きます。しかも、生きる力もあわせてついてきます。 「手は外に出ている脳」ともいいます。手を使えば使うほど、脳も発達します。急がばまわれと言うでしょう。 まずは、じっくりと基礎づくりをさせたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 日曜日のお昼ごはんづくり、洗濯、掃除などに家族みんなで取り組んでみるのもいいですね。 ページの先頭に戻る (12)読書のすすめ読書は心の栄養です。本を読むことで、体験したことのない多くの事柄を知り、物の見方や考え方を学び、人間としての感性を磨くことができます。 本から得た知識や考え方が肥やしとなって、考えを豊かにし、様々な場面で支えとなってくれることもあります。本は、生涯の友となります。 さて、本を好きにするためには、本のある環境をつくることです。いつでも手の届く所に本が置いてあるよう、気を配りたいものです。その中で、自分の欲しい本と巡り合うことができれば、とても喜ばしいことです。特に高学年の子どもは知的好奇心や情緒が発達する時期でもあり、夢や希望、素晴らしい生き方などが描かれた本は子ども達の宝物となるでしょう。ですから、学習に直接役立つような本だけでなく、子ども達の情緒を育むような本等、偏りなくそろっていれば申し分ありません。 といっても、家庭にありとあらゆる本をそろえておかなければならないというのではありません。地域の図書館を利用したり、本のリサイクルなどを活用したりしてもよいでしょう。とにかく、家庭で本に親しむ雰囲気をつくっていくことが、子どもにとって一番の読書環境といえます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 毎日、短い時間でいいから、テレビを消して、家族で本を読んでみませんか。親が熱中して本を読む姿を見せるのもいいことです。 ページの先頭に戻る (13)家庭学習のポイント「家庭学習って、宿題のこと?」と思う人もいるかもしれません。 宿題をすることも家庭学習の一部ですが、すべてではありません。家庭における学習は、 生きた知恵を得ることと学校などで学んだ様々な知恵を実際に生かしていくことが大きなねらいとなります。 とはいっても、実際は「何をすればいいの?」「どんなことをさせたらいいの?」と悩む子どもや親もいます。 そんな子どもには、学校で学習した内容をもとに家庭での学習を計画させるのです。はじめは、 反復練習を中心に、次は自分なりに教科書や参考書をまとめることから取り組ませ、 だんだんに質の高い学習へと進んでいけばいいのです。まずは、机に向かわせ、 勉強するのだという気持ちを起こさせましょう。 興味をもったら、何でも取り組ませましょう。実は、それが大事なのです。頼まれ仕事ではなく、 新しい知識を学び、身につける楽しさを味わわせたいものです。しかも、習慣となればいうことはありません。 徐々に「自分で学習する力」がついていきます。
机に向かっているタイミングをうまくとらえ、「がんばってるね」の一言をかけてあげましょう。 ページの先頭に戻る (14)集団遊びを子ども達へガキ大将を中心に毎日空き地に集まっては様々な遊びをしている子どもたちがいる風景 は、今はあまり見られなくなりました。 その時のガキ大将は必ずしも成績の良い子だとは限りませんでした。腕力が強く、 しかし、幼い子や身体の弱い子には気配りができるやさしさをもった子がなることが多かったのです。 幼い子はその集団の中で、大きい子ども達の行動を見て、ルールを身につけていきました。 缶けり、宝さがし、鬼ごっこ、ベーゴマ……、身の回りにある物を工夫 した遊びに夢中になったものです。群れて遊ぶ子ども達の文化が作られ、 そこから子ども達は社会的なルールを身につけていきました。 ところが、社会の急激な変化に伴い、大人達の価値観も変わっていく中で、 子ども達の世界も変わってきました。今や、日常生活の中で子ども達は年の違う子ども達と 過ごすことはめったになくなり、ゲームやスマホ等の遊びが中心となり、 自然や生きものを相手にすることも少なくなってしまいました。 そこで、青少年教育施設や公民館等では、失われつつある集団遊びの場を復活させ、 子ども達に体験させようと様々な事業を組んでいます。参加した子ども達は皆、生き生きとした表情で 仲間と活動しています。この満足しきった楽しそうな顔が、子ども本来の姿であり、 昔も今も変わりはありません。日常生活の中でも、子ども達が群れて遊べるような環境や機会を 積極的に作り出していくのも大人の大きな努めです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 時には、地域の子ども達を集めて、一緒に遊んでみませんか。 すべての親が付きっ切りになる必要はありません。子ども同士でふれあう機会の中で、 子ども達はおのずから成長していきます。 ページの先頭に戻る (15)たくましい子どもを育てる失敗体験学校で一、二を争う成績のA君とB君が有名高校を受験し、いつもA君を追い越せないでいた B君だけが合格したそうです。A君は、B君を逆恨みし、慰めにたずねてきたB君に対し、 「世界で一番憎い相手」と言って会おうともしません。「僕だけ受かってごめんね」とだけ言って、 涙をいっぱいためて帰ったB君を見て、A君は恥ずかしさで胸がいっぱいになったそうです。 「自分だったら、落ちたライバルを慰めにいっただろうか。人の事を考えもしないで、 自分のことばかり考えるような人間は落ちて当たり前。本当の人間にするために天は僕を落としたんだ」と A君は自分を責めたそうです。「今まで思うようになることだけが幸福だと考えてきたけれども、 B君のおかげで思うようにならないことの方が人生にとって大切だということを知った」と A君は述べています。(東井義雄著「根を養えば樹はおのずから育つ」より) 一家族あたりの子どもの数も少なくなっている今、子どもにかける手はとても多くなってきました。 すっかりおぜん立てをしてしまったところに子どもが登場し、何の苦もなく課題をクリアしていきます。 失敗することなく、あたかも自分だけの力ですべてが解決できると勘違いをしてしまったまま 成長したらそれこそ大変です。自力で前に進まなければならなくなったときに思うようにできなかったら、 そこで挫折してしまいます。失敗や挫折をすることは長い人生の中では、ままあります。 小さい時から失敗しても、それで終わりにするのではなく、次に成功するために努力するという 経験を積ませていくことが大事です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 親だって失敗したことはあるはずです。さりげなく、失敗したときの話を聞かせるのもいいですね。 ページの先頭に戻る (16)親子でチャレンジ アウトドア阪神大震災の時に、一早く救援ボランティア活動に駆けつけた方の話です。 被災者の方々に何が欲しいかたずねたところ、温かいごはんが食べたいというのが 最も多い声だったそうです。「しまった、米を持ってくるんだった」と声をあげたら、 「米ならあるよ」との声、そこで、瓦礫の中からつぶれた鍋と木切れを集め、ごはんを炊いたそうです。 ふつふつ湯気があがり、ごはんの炊ける甘い香りが辺り一帯に漂いました。あったかいごはんは飛ぶように売れ、 みんなで炊き立ての味をじっくりと何日かぶりに味わいました。「ごはんって、こうして炊くのだったのね。 忘れてたわ」と60歳代の女性がぽつり。炊飯器がなくても、電気がなくてもごはんは炊けるのです。 アウトドア志向の時代といわれるこの頃、夏になると豪華なキャンプ道具を積んだ車が 県内を駆け巡ります。至れり尽くせりのキャンプ場もできてきました。しかし、野外活動は、 特別な設備や場所がなくてもできるのです。家の近くで、まずは親子で火をおこすことからスタート。 以外と難しいものです。力を合わせなければなりません。火がおきたら、ありあわせの材料で食べる物を 作ってみましょう。煙も灰も普段味わえないスパイスになります。嫌いなものだって、 おいしく食べることができるでしょう。親子で調理をしながらだったら、会話もはずみます。 子どもにとって、親のやることを直接まねができるいい経験となります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 何かをつくる楽しさや、力を合わせることの素晴らしさを子ども達に伝えるには、野外活動は最適です。 家の庭でもいいのです。アウトドア体験をしてみませんか。 ページの先頭に戻る (17)地域とともに子育てを子ども達は、家庭だけではなく学校や地域から様々な影響を受けながら育ちます。 特にも、地域の中からは、人間として生きていくための知恵を、実践を通して教わります。 地域から学んだことがらは、生きていくための大きな支えとなります。 自分の住んでいる地域の素晴らしさや地域の人達に支えられて生きているのだという 実感を味わわせるためにも、地域で行われる様々な活動に親子で参加することが大事です。 あなたのお子さんは、大人に混じって地域の祭りでみこしをかついだり、 地域の公園の清掃をしたり、地域のスポーツ大会に参加したことがありますか。 地域の自治会等では、世代を超えた様々な活動が行われています。このような時こそ、 地域活動に子ども達を参加させる良いチャンスです。いろいろな人達と交流を深めることで、 地域の子どもとして認められていきます。地域の大人の温かなまなざしの中で子どもが成長できることは、 子どもにとっても親にとっても素晴らしいことです。地域の中に融けこんでいけば、「隣は何をする人ぞ」 といった感じはなくなります。子育てについての不安や悩みだって気軽に話し合えるような 関係もできてくるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ よそのおじちゃん、おばちゃんに一人前に扱われると、いっぱしの大人になった気がして、 うれしいものです。 ページの先頭に戻る (18)身につけさせよう生活習慣「起きなさい」と毎朝叫んでいませんか。親の手助けなしに自分で起きる。これが一日の始まりです。 「おはよう」とあいさつしていますか。これは、一日を明るく暮らすための最初の一言です。 まずは、親の方から声をかけましょう。 朝も夜も「いただきます」と家族みんなで顔を合わせて食事ができるといいですね。 食事の後は、少し勉強でもしましょうか。それとも食事の前に勉強を済ませてしまいますか。 少しでいいのです。毎日決まった時刻に決まった時間勉強するという習慣をつけるには、 小学校高学年はちょうどよい時期なのです。 さあ、眠る時間がやってきました。ゲームやスマホは切り上げさせましょう。 さもないと、中学、高校になって、とめどもなく夜更かし朝寝坊タイプになってしまいます。 これらのことが毎日同じリズムで実行できるようにこころがけましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもによい生活習慣を身につけさせるコツは、いたって簡単です。それは、 明日といわずに今日から実行することです。 ページの先頭に戻る (19)わが子のもち味を大切に料理の上手な子(特技)、親切な子(性質)、いろいろな事に興味を示す子(興味関心・意欲)など、 人は誰でもその人にしかない「もち味(特徴)」を持っています。 この長所を伸ばさない手はありません。その子の持つ良さをどんどん伸ばすことこそ、 子育ての基本となります。「長所を伸ばすと、短所は弱まる」との昔からの言い伝えもあります。 皆さん、お子さんの長所がすぐに思い浮かびますか。一つ、二つと浮かんでくる方は、 子どもにとっては実に素敵な親であるといえましょう。逆に、子どもの短所だけが浮かんでくる方は ちょっと考えものです。「こんな事も、あんな事も何もできない」などという目で子どもを見れば、 子どもの良さを見つけられるはずがありません。そのようなタイプだと思った方は、 見方を変えてみてください。日常生活の中から必ず長所が見つかるはずです。 それがお子さんのもち味なのです。そのもち味を大事にして、伸ばしてあげましょう。 「もち味」を発見する手がかりは、「興味と関心」です。何をしたがっているかをわかってください。 最初は幼稚で次元の低いものかもしれませんが、好きなこと、 やりたくてたまらないことを積み重ねていくうちにしだいに高度なものに発展していきます。 その中で、学ぶ意欲や生きる力が身についていくものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子どもの行動を規制するばかりでは、子どものやる気をそいでしまいます。 長い目で見守ることが大切です。 ページの先頭に戻る (20)さまざまなタイプの親がいるけれど親に似ていない子なんて、一人もいません。顔の形はもちろんのこと、言動や価値観にいたるまで、 「親の言う通りの子」よりも「親のやる通りの子」が育ちます。それは、 親の姿を毎日見て育つからに他なりません。良くも悪くも親の姿はそのまま子どものお手本になります。 お手本に望まれる第一の条件は、何と言っても親が仲良くすることです。 円満な家庭では、思いやる心も育ち、おのずとコミュニケーションも図られます。 第二の条件は、家庭の中に愛情があふれていることです。信頼し、尊敬し合い、 家族一人ひとりを大切にする家族であれば、子どもは自分の居場所がわかります。 「人のふり見て、我がふり直せ」と言われますが、あなたも次にあげるような親になってはいないか、 時々、振り返ってみませんか。 【溺愛型】 この世の中に我が子ほどかわいいものはないと思うのは当たり前のことです。 必要以上に世話をやき、べったりくっついていると、依頼心の強い子になりがちです。 一人前の人間として扱うことが大切です。 【矛盾型】 子どもが同じ事をしても、その時の気分で叱ったりほめたりする気まぐれな親だと、 子どもはどう対応したらよいか迷ってしまいます。 親の顔色をうかがう子どもになりがちです。 【干渉型】 親がやたら手も出し口も出し、指示や注意が多すぎると、指示がなければ動けない子どもになりがちです。 自分の力でやってみようという気持ちをつぶしてしまいかねません。 【放任型】 親が子どもに無関心で、放りっぱなしだと、子どもは愛情に飢え、情緒不安などから攻撃的になったり、 素直さに欠けたりすることがあります。 「自由にさせる」ことは、「放任する」ことではありません。 ページの先頭に戻る (21)しっかりほめて、ピリッと叱る料理に甘辛味はつきものです。子育てにだって、甘さ(ほめる)と辛さ(叱る)の両方が必要です。 成長する節目にほど良く味付けしてこそ、きりりとした子どもが育ちます。 「七つほめて、三つ叱れ」などと言われますが、その子どもの性格によりけりで、 一様には言えないでしょう。ほめて伸びる子もいれば、叱って伸びる子もいます。 子どもにも感情があるので、叱られるよりはほめられるとやる気をおこし、 前向きに行動する方が多いといえます。しかし、おだてたり、こびたり、 ほめちぎったりと過剰に対応するのは考えものです。良かったところを的確にとらえ、 タイミングよく、しかも心の底からほめることができれば最高です。 小学校高学年ともなれば、事実の背景や因果関係を理解することができます。だからこそ、 事実に即し、根拠を明確にしてからほめたり、叱ったりすることが大切です。先入観やその場の雰囲気、 感情などで叱ったりするのは考えものです。なぜなら、統一性を欠いた対応のしかたに子どもが納得できず、 親への反感だけが膨らみ、逆効果になってしまうからです。 命にかかわること、人道的でないこと、社会的なルールに反すること等、 たとえどんな事情があっても厳しく教えなければいけないことがあります。 それらをないがしろにして、箸の上げ下ろしに代表されるような細かなことにだけうるさく口を 出すのではいけません。 甘辛は、子育ての大切な味付けです。心から愛情をこめたほめ方、叱り方を工夫したいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 家族みんなが同じ考えで、子どもに対応することが大切です。人によって対応の仕方が違えば、 子どもは混乱します。 ページの先頭に戻る |