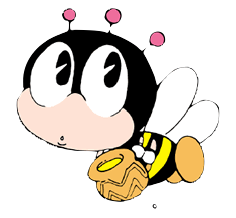

|
トップページ > 子育てワンポイントアドバイス > 子育てQ&A
「まなびネットいわて」リニューアルのお知らせ令和5年4月1日、まなびネットいわてのページをリニューアルしました。「子育てワンポイントアドバイス」新ページは下記をご覧ください。 新URL:https://manabinet.pref.iwate.jp/index.php/kosodate/1point-menu/ |
子育てワンポイントアドバイス
子育てQ&A
|
(1)あんよは上手 (2)断乳 (3)お腹の赤ちゃん (4)さよならおむつ (5)三つ子の魂 (6)予防接種 (7)身の回りの危険 (8)アトピー性皮膚炎 (9)虫歯を防ぐ (10)指しゃぶり (11)絵本・テレビゲ-ム (12)言葉の始まり (13)いっしょに遊ぶ (14)乱暴と泣き虫 (15)早期教育 (16)心の基地 (17)ほめる・しかる (18)ジジババの力 (19)家族と近所 (20)保育園・幼稚園 |
(1)あんよはじょうず【Q】 うちの子は、もうすぐ満1歳の誕生日をむかえますが、まだ歩けません。 近所で同じくらいの子はとっくに歩き始めています。 発育が遅れているのでは、と心配です。(11か月半男児の母) 【A】 一人歩きも個人差があり、心配することはないと思われます。誕生日をむかえるまでの発達段階があって、 たとえば、つかまって立っていられるのが7か月~9か月、つたい歩きは、8か月~10か月、 歩けるようになるのが、12か月~14か月頃がめやすとなります。 このように一つひとつが出来てゆくのには幅があり、個人差があります。 お子さんの様子を良く見つめて、手をかしたり、勇気づけをしてあげてください。 ただし、バランスのとれない歩き方で気になる時には、 かかりつけのお医者さんに相談するのもよいと思います。 ◆◇パパへのワンポイントアドバイス◇◆ 日本版デンバー式発達スクリーニング検査によるデータがあります。 上手に歩くには、11か月頃で25%、12か月で50%、13か月頃で75%、 14か月を少し過ぎて90%と言われています。参考にしてみてください。 ページの先頭に戻る (2)断乳【Q】 うちの子は、もうすぐ2歳になるのですが、なかなかおっぱいを離しません。 自然に離れるものと待っていたのですが、断乳するよい方法はないでしょうか。 (1歳8か月女児の母) 【A】 お母さんの腕に抱かれて満足そうにおっぱいをのんでいた赤ちゃんも、 4・5か月になると離乳食を食べられ、1歳頃には、ほぼ大人と同じものが食べられるようになります。 その頃になると、「おっぱい」は甘えや心理的な安定の要素が強くなりますが、 「おっぱいは赤ちゃんがのむものだよね。○○ちゃんはもう大きくなったからごはんを食べようね。」と、 お母さんの言葉で話しかけ、納得させて無理なく離しましょう。膝の上で絵本を読んでやる。 手を握って眠りにつかせるなど充分なふれあいも忘れずに。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ -私の断乳法- (滝沢村 Sさんの場合) 息子が2歳頃、ごはんも良く食べるのに、どうしてもおっぱいがやめられないでいたときに、 大好きなクマさんの顔をおっぱいのところに大きく描いてみました。息子は目を丸くして驚いて、 それからおっぱいを吸おうとしなくなりました。このときに大事なことは、 こわい顔でおどかしてやめさせるのではなく、やさしく、かわいい顔で喜んでやめるようにすることですね。 ページの先頭に戻る (3)お腹の中の赤ちゃん【Q】 お腹の中の赤ちゃんは、お母さんの語りかけや子守歌などに反応を示すことがあると聞きました。 お腹の中の赤ちゃんにお母さんの気持ちが伝わるものなのでしょうか。 (26歳の主婦 妊娠5か月) 【A】 お腹の中の赤ちゃんの10か月は生まれてから必要な機能を発達させる大切な期間です。 その間お母さんのリズミカルな心臓の鼓動で情緒を安定させます。 また、お母さんの態度や感情をかなり微妙に区別でき、胎生7か月頃からそれに反応し始めます。 お母さんは、お腹の中の赤ちゃんを心よりかわいいと感じ、健康で正常に育つことを願い、 お腹を優しく撫でたり言葉をかけたりし、慈愛に満ちていればお腹の中の赤ちゃんもそれを敏感に感じとり、 お母さんへの信頼と愛情を抱いて快い成長を続けるのです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 口では子どもを欲しくないと言い、胸の内では妊娠を喜んでいるような矛盾した感情が母親にある場合、 母親から2つのメッセージを受けるため胎児の精神は混乱し、無気力になる傾向があるといわれます。 母親の迷いのない信念が胎児の精神を強く育てます。 夫と妻は互いにいたわり合い、幸せな夫婦であることが母胎を安定させ、胎児によい影響を与えます。 ページの先頭に戻る (4)さよなら、おむつ【Q】 3歳になるのになかなかおむつにさようならができません。紙おむつを使っているせいでしょうか。 (3歳女児の母) 【A】 紙おむつを使っていると、おむつによる不快感が育たずおむつ離れが遅いのではないか・・・、 などと言われていますが、必ずしもそうとは限りません。 布おむつとちがい紙オムツの場合はどうしても交換回数が少ないようです。 紙オムツは上手に利用して欲しいものです。あせらず、成功したらほめ、失敗しても 「おしっこ出てよかったね」と、決しておこらないことです。 おむつをはずす時期は個人差がありますので温かく見守り発達を待ちながら、 自立への手助けをしてあげましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 紙おむつは、外出の時に利用するというように、場合によって使い分けるなど、 上手な利用の仕方ならよいのですが、単に育児の手間を省けるからという理由で、 全て紙おむつで処理しようとすることは避けたいものです。 赤ちゃんに語りかけながら、おむつがぬれていないかどうか手を差し伸べて肌にふれ、 おむつをかえる時間を惜しまないこと。これが育児の第一歩でしょう。 ページの先頭に戻る (5)三つ子の魂って?【Q】 「三つ子の魂、百まで」という諺は昔からいわれていることですが、 それは具体的にいえばどういうことなのでしょうか。 養育にあたる親はどんな心構えが必要でしょうか。(2歳半男児の母) 【A】 この諺は、3歳児を中心とした幼児期の育て方、しつけ方は、その子の、 のちの人生に大きな影響を与えるということを言っているのです。 出生から3歳までの3年間は、脳の発達する重要な時期であり、 いわば「脳の土台づくり」の時なのです。そして知的、社会的、性格的なそれぞれの面で、 その基礎ができあがると同時に、親子関係の絆を強める「愛の育児」が 最も求められる大切な時期でもあります。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 「愛の育児」 にとって一番大切なことは、親子の間に「愛と信頼感」 を育てることです。 そのためには親が一対一で子どもの相手になり、「愛の充電」(肌のふれあい。笑顔のふれあい。 言葉のふれあい)を十分にしてやることです。例えば、ひざに乗せる、頭をなでる、 だっこする、おんぶする、手を握る、添い寝する。また、笑顔で「目と目の見つめ合い」 「語りかけ」など父親も母親も子どもとの「ふれあい」の機会をふやし、 親子の絆を強めていくことです。それが知的、社会的、性格的に良くなっていくことになるのです。 ページの先頭に戻る (6)予防接種【Q】 ポリオの予防接種について質問します。ちょうど接種の日に熱があり下痢気味だったため ワクチンをうけられませんでした。ポリオになるのでしょうか。他のワクチンもまだやっていません。 (10か月女児の母) 【A】 予防接種をしていないとポリオにもかかる可能性はあります。 しかし、実際には日本では近年患者は出ていません。従ってすぐにポリオになる心配は不要です。 春と秋に集団接種されますので公報に目を通しておいてください。 いろいろなワクチンの接種計画はかかりつけの小児科医や、 健診の際の育児相談の場でアドバイスをもらいましょう。 母子手帳の予防接種のページに予定を鉛筆で記入しておくのも良いことです。 何かと延びのびになって病気になって後悔することも多いようです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ~よいワクチンとは~ ○その病気の伝染力が強く、重症または強い後遺症を残しうる病気に対したもの。 ○効果が充分であること。 ○副反応がないこと。 ポリオやBCG(結核ワクチン)はほぼこの条件を満たしています。 ポリオはもう少しでこの地球上から撲滅できる所にきています。ワクチンのおかげです。 三種混合(百日咳、ジフテリア、破傷風)、ハシカ、おたふくカゼ、そして男の子にも風疹、 更に水疱そう、日本脳炎など、いずれも自然の病気になるよりはずっと軽くすんでしまいます。 やはり予防接種が有利です。 ページの先頭に戻る (7)身の回りに潜む危険【Q】 先日、ポットの熱湯が赤ちゃんの手にかかってしまいました。急いで水で冷やして、 たいした火傷にはなりませんでした。もっとひどかったらと思うとぞっとします。 事故に対する注意などどんなことが大切ですか。 (2歳男児の母) 【A】 そうです、すぐに水で冷やしてください。ゆるやかな流水が良く、充分に冷やせば、 痛みも楽になります。いかに早く、長く冷やしたかで、治るまでの期間や、後遺症の重さも変わります。 赤みがはっきりしている時は医師にみせましょう。 事故は、治療よりもともかく予防が第1です。タバコ、ピン、コイン、 ボタン電池など家や身のまわりには危険物がいっぱいです。子どもの目の高さで常に点検、 かたづけを心がけましょう。家庭の風呂や整理ダンスの上にも注意を向けましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ やけど、水の事故、交通事故、窒息、誤飲。 いずれもほんの一瞬です。 「目を離さない、手を離さない、心を離さない」はふだんからの心掛け。しっかり身につけること。 こうしてやさしいお母さん、よいお父さんになり、家族のみんなの中で子どもたちを守れます。 乳児の死亡率も下がり、病気にも強くなってきた子どもたち。 しかし、事故で生命をおとしたり、後遺症をのこすケースが少なくありません。保護のもと、 事故にまきこまれないしつけや訓練にも心がけたいものです。 ページの先頭に戻る (8)アトピー性皮膚炎【Q】 2歳の男の子です。手、足、身体に湿疹が多くて困っています。 アトピー性皮膚炎といわれました。何かアレルギーが関係あるのでしょうか。 予防や治療はどのようにすればよいのでしょうか。 【A】 ○皮膚表面の保護層を守る 汗、ほこり、土、乾燥、掻きキズは湿疹を悪化させます。 また、硬い布で頻ぱんにふくのは皮膚表面を削り荒らします。ぬらした柔らかい紙か布で清潔を保ちます。 必要に応じで安全性の高いクリームで保護するのも一法です。 ○軽いうちにまめに手入れする 軟膏は2種類。ステロイド入りと、入らないものを医師の指示で使いわけることも大切です。 体質改善の薬も時に効果を発揮することがあります。良く相談し根気よくスキンケアをいたしましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 湿疹の要因は子どもの体質、食事の内容、遊びの種類、季節、家やまわりの環境、 疲れや年齢など千差万別で治療は一人ひとり違います。アレルギーの原因も卵、 ハウスダスト、ダニなど。また、これを時には細菌やカビが悪化させることもあり、 いずれも必ず医師の検査や指導に基づいてください。悪化因子をみつけるには食事、 生活表をつけるのも一法です。食事は原則として特定のものを多量にとるのではなく、 多種類を少しずつ、良く噛んで頂きましょう。離乳食は早すぎぬよう。ことに”好きだから多く”は 避けることが大切です。 ページの先頭に戻る (9)虫歯を防ぐ【Q】 元気な長男は、歯ブラシを手に喜んで歯磨きをするのですが、仕上げ磨きをしてやろうとすると嫌がります。 このままではむし歯ができるのではないかと心配です。 (2歳2か月男児の母) 【A】 2歳頃になると、乳歯がきれいにはえそろいます。この頃から、 習慣づけと興味をもたせる目的で歯磨きをさせることが大切ですが、 一人できれいに磨けるようになるにはまだ時間がかかります。 しばらくはお母さんの膝の上に寝かせて、口の中を点検しながら仕上げ磨きをしてあげることが必要です。 いやがるときは、脇からちょっとおさえて最もむし歯になりやすい上の前歯、 奥歯のかみ合わせ部分だけでも手早く磨いてあげます。 また、定期的な歯科検診はむし歯の予防と早期発見に役立ちます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ~おやつとむし歯~ おやつは子どもにとって、とても楽しみなものです。甘いものに片寄ることなく、 一日の食事の一部と考え、上手に組み合わせを工夫したいものです。 ○時間と量を決め、だらだら食べない ○素材のおいしさを味わえるものや三回の食事で摂りにくいものを取り入れる。 あめ、チョコレート、ガム、スナック菓子、甘い飲み物は控えめに。 ○食べた後はブクブクうがい、できなければ番茶、水を飲む習慣を。 ページの先頭に戻る (10)指しゃぶり【Q】 共働きでこれまでは祖母が日中世話をしてくれていましたが、 満3歳になりこの4月から保育所に通わせました。ところが最近指しゃぶりがとても多くなったようで、 テレビなどを見ている時も指をしゃぶっています。 (満3歳女児の母) 【A】 離乳、歩行、生活習慣の自立・・・と、子どもは次第に親から離れるようになりますが、 この過程で子どもの心は親に甘えたい気持ちと自立したい気持ちの間で揺れ動きます。 特に保育所や幼稚園に通いはじめると集団生活の緊張も加わり、子どもの親に甘えたい 気持ちが強まり、このような時一旦止めた指しゃぶりやおなじみの毛布の端をしゃぶる などの行動が多くなります。たいてい新しい環境になれてくると自然に減っていくものですが、 短時間でも子どもを抱いてあげたり、子どもと身体的に触れ合う時をもつことも大切です。 ページの先頭に戻る (11)絵本・テレビ・ゲーム【Q】 幼稚園に通っている4歳の男の子です。家に帰るとテレビの前から離れません。 好きな番組がない時はテレビゲームをしたり、ビデオを見ています。 食事の時もテレビから目を離しません。好きなだけ見せておいてよいのでしょうか。 【A】 テレビは動きのある画像のリズミカルな音楽など子どもばかりではなく、 大人にとっても関心をひく条件が揃っています。テレビを見るときには家族みんなで話し合って、 けじめをつけ、番組を選んでやったり、つける時間を決めてみんなで守るなどの配慮が必要でしょう。 また、4歳は言葉も想像力も豊になる年齢です。テレビからの一方的な刺激ばかりでなく、 絵本を読み聞かせてやったり、昔話をしてやるなど、親子で語り合ったり、 ふれあいのできるものをたくさん与えてやりたいですね。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ~絵本について~ 絵本は子どもが最初に出会う本です。赤ちゃん用の絵だけの本から、 読み聞かせのものまでいろいろな種類がありますが、良い絵本を選んでやりたいものです。 選択のポイントとして、絵はできるだけグロテスクなものは避け自然な印象を与え、 また、そこに書かれている文は絵とマッチしたもので、こどもが豊かなイメージを持ち、 心に訴えるような内容のものを選んであげましょう。 なによりも、親自身が絵本に関心をもち、好きな絵本を選んであげられるとよいですね。
ページの先頭に戻る (12)言葉の始まり【Q】 うちの子はまもなく満2歳の誕生日を迎えますが、言葉の発達がおくれているようで、 まだ「ママ、イナイ」、「ブーブーイッタ」とかいうだけで同じ年齢の子どもさんに 比べておそいようで心配です。 (1歳11か月男児の母) 【A】 1歳の誕生日頃になると子どもは、「ママ」とか「ウマウマ」とか意味のある言葉を発するようになります。 それから次第に言葉数もふえ、、「ウマウマ、オイシイネ」、 「オテテ、バッチ」など2語文へと進み、子どもは自分の気持ちを言葉で上手に表現することが できるようになっていきます。でも言葉の発達の面でも個人差は大きいのです。 全般的に著しい発達のおくれがない限り他の子どもさんと比較して一喜一憂せず、 たどたどしい表現でも子どもの表現したい気持を十分きいてあげることが大事です。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 育児書や発達心理学の本などには、子どもが何か月になると「ウマウマ」などの一語文から 「ウマウマほしい」、「ウマウマあった」などの二語文に移っていくとか、 何歳になると名詞や動詞はいくつ位使えるようになるとか記されていますが、 およその目安としては参考になるでしょう。しかし、言葉の発達にとって大事なことは、 子どもの中に「伝えたい気持ち」が起こり、「きいてもらった」と喜びを経験することです。 言葉の数や形式にあまりとらわれずに、言葉以前の親子の情緒的コミュニケーションも大事にしましょう。 ページの先頭に戻る (13)いっしょに遊ぶ【Q】 2歳間近の男の子です。この頃いたずらが激しく困っています。 おもちゃを与えてもすぐあきていだずらを始め「ダメ」と禁止の連発。 目も離せない状態で親子でイライラしています。どうしたらいいのでしょうか。 【A】 2歳という年齢は自分でやりたいと思う気持ちが盛んに表われ、冒険心も芽生え、 何にでもふれたり、さわったりという行為を繰り返しやることで、試し、確かめ、 いろいろな事を学んでいく大切な時期です。危険のない程度に一人で探索させることも必要ですし、 また、少々乱暴な位に体を動かした遊び、追かけっこやまねっこなども大好きな頃です。 お母さんが相手になって一緒に遊んでやることで遊びが一層楽しく心も体も満たされていくことでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 布団の上でのでんぐり返りやすもう、くすぐり遊びなどは、スキンシップを兼ねた楽しい遊びです。 戸外ではかくれんぼ、ボール遊び、追かけっこ、また、静的な遊びとして、ままごと、 手遊びなどは親子で手軽に楽しめる遊びと言えるでしょう。小さい時だからこそ、 物で遊ぶのではなく信頼できる親と楽しく遊ぶことが大切です。 子どもと一緒に遊ぶことは根気のいることですが、遊ばせてやっている気分では遊びは続いていかず、 つまらないものになります。 親も童心にかえり一緒に楽しく遊んでほしいものです。 ページの先頭に戻る (14)乱暴と泣き虫【Q】 1歳半の男の子ですが、歩き始めた頃から誰かれかまわず出会った人、 特に子どもをひっかいたり、たたいたりします。相手が小さい子どもだと泣き出したりしますし、 親もつい押さえたり、叱ったりしてしまいます。 【A】 歩行が自由になった子どもの世界は急速に広がります。 この頃の子どもにとっては全 てが新しく珍しいものですが、まわりの人々や、 あるいは事物とどのようにつきあえばよいのかまだわからないのです。 この頃の子どもは何にでもさわり、ためしてみます。親にはひっかいたり、 たたいたりと思える行為も、子どもにとっては挨拶や相手を知るための行為なのでしょう。 子どもは試行錯誤しながら人とのつき合い方も学んでいきますが、 相手の子どもが泣き出すような場合は「痛かったんだって、こめんね。」と 親も一緒におやまってあげたらどうでしょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ~泣き虫で困っています~ 泣くことは、笑いや怒りと同じ感情の表現です。 1歳数か月頃の子どもは言葉で言えないことを泣いて自己主張するのです。 初めは泣くしかできなくても、大きくなるにつれて表現力がつき、 他の方法で気持ちを伝えるようになります。泣いている時、今は「くやしかったのね」と 気持ちを分かってあげるだけでいいのです。 ページの先頭に戻る (15)早期教育【Q】 隣の子は、3歳で英語を習っています。漢字を書ける子もいます。 うちの子は、まだ、ひらがなの読み書きもできません。遊んでばかりいて、大丈夫でしょうか。 今のうちから何かさせておかないと学校に上がってから苦労するのではないかと不安です。 (4歳女児の母) 【A】 子どもは教えればかなりの事ができる様になる場合があります。 けれども、無理に背伸びをさせたり、生活とかけ離れた形で教え込まれたものは、 長続きしないばかりか、「○○嫌い」を作ったりもします。時期がくれば、 興味・関心を持ってじっくり取り組む子になります。 そのためにも、幼児期には、好きな遊びをたっぷりさせましょう。生活や、 遊びの中で興味や疑問にていねいに応えたり、学ぶ力を育てていきましょう。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 周囲に流されて親が早期教育に駆り立てられて不安になったり、あせったりすることは禁物です。 子どもには、一人ひとりその子なりの学び方があります。その子の興味や関心を大切にして相手をしましょう。 長い目で一人ひとりの育ちを見守り、その子が今、興味を持っている事、 伸びようとしているところを手助けしましょう。 ページの先頭に戻る (16)心の基地【Q】 うちの子どもは、外が大好きです。ちょっとのスキに家から飛び出し、 〝どこにいっ たんだろう〟と心配しているうちに帰ってきてほっとしますが、 それもつかの間、また出ていってしまいます。何だかせわしくて目が離せません。 (3歳男児の母) 【A】 乳児期には、母親の膝もとを基点にして遊んでいた子どもも、 1・2歳になると遊びを次々に変えながら自分の確保したおもちゃや自分のすることを 「見て!」という要求を示すようになってきます。 3歳頃になると、子どもの活動範囲は家から戸外へと広がります。 小さい争いを起こしながらも楽しく遊んでいるのに、友だちとの遊びから離れて親のもとへ帰り 相互に確認しあって、また安心して遊びにもどります。子どもにとって親は、 「母港」であり 「心の基地」なのです。親は子どもの気持ちを受けとめてあげながらあたたかく 見守りたいものです。 ページの先頭に戻る (17)ほめる・しかる【Q】 ほめ方や、しかり方が良くわからなくて困っています。上手なしかり方を教えてください。 (4歳女児の母) 【A】 大人でも子どもでもほめられるとうれしいものです。ほめられることによって自信を持ち、 これからも続けてやっていこうと思います。一方、しかられてはやっていけないことを学びます。 この頃甘やかし、しかるべきときもしからない親が増えています。 そのためにわがままで忍耐力の弱い子どもが多くなったとも言われています。 ほめる、しかるは車の両輪でどちらも欠かせません。子どもをどのように育てていったらよいか 家族で良く話しあって、一貫したしつけに当たっていきたいものです。
何よりもしかるよりもほめることを多くして子どもに自信を持たせるようなしつけ方が大事です。 ページの先頭に戻る (18)おじいさん、おばあさんの力【Q】 育児について、おばあちゃんと意見が合わないことがあって悩んでいます。 (3歳女児の母) 【A】 家庭にお年よりや働き盛りの両親や子どもたちがいてむつまじく過ごすしていることは、 家族にとっては何よりも幸せなことですが、ときにはそれぞれの年代で考え方や、 やり方が異なってぶつかることもよくあることです。 常日頃お互いざっくばらんに語り合える家族の雰囲気づくりに努めましょう。 家族のかなめは父親、そして母親の細やかな心づかいや体験に裏づけられた祖父母 それぞれの持ち味を生かしていく家庭生活の中で、子どもたちは人間関係のあり方を学び、 互いに思いやる優しいこころを育てていきます。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ ~祖父母の願いと知恵~ 祖父母から見た家族(子や孫)とのつきあい観(※老人の生活と意識)によると、 いつも一緒に生活できるのがよい(53.6%)、ときどき会って食事や会話をするのがよい(37.8%)で、 同居志向型が多く、また老人にとって一番大切なものとして、「家族、子ども」が(88.2%)と、 イタリアに次いで非常に多いことがこの国際比較調査に表れています。 「亀の甲より年の功」の自信を持ち、一方「昔は昔、今は今」と割り切って若い人たちとすすんで交わり、 祖父母自身が生きがいをもって家庭の団らんを楽しみたいものです。 「老人の生活と意識」(第3回国際比較調査結果報告書 平成3年12月総務庁長官老人対策室) ページの先頭に戻る (19)家族、おとなり、近所【Q】 近所に同じ年頃の子どもがいないので、友だちと遊べません。みんなと仲良く遊ばせたいのですが。 (3歳女児の母) 【A】 この頃、あなたと同じような悩みを持つ親の声が多く聞かれるようになりました。 子どもは遊びによって成長していきます。遊びによって遊びの楽しさや面白さを知ったり、 一方がまんや、許すことを学んだり、自分の言いたいことを主張したりして、 次第に社会生活のルールを身につけていきます。子どもに遊び場や友だちづくりをしていくためには、 まず同じ地域に住む親同士が親しくなって、育児のことなどについてもざっくばらんに 語り合えるようにしていきたいものです。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 現在「1.37ショック」などと問題提起されているように少子家族が増え続けています。 友だちと遊べる環境を作っていくためにいろいろと知識を働かせたいものです。 例えば、地域での行事に親子で参加してみてはいかがでしょうか。ラジオ体操、お祭り、盆踊り、 探鳥会など多彩な行事があります。 共に行動しているうちに子どもは次第に積極的になって皆と一緒に遊べる友だちができたとか、 親同士も仲間ができるようになったというようなうれしいケースをよく聞くことがあります。 ページの先頭に戻る (20)保育園や幼稚園【Q】 今年の4月に保育園に入園した4歳の女児です。5月下旬から登園を渋るようになり、 機嫌をとってなだめても、泣きながらの登園です。友だちが遊んでくれないとか、 いじめると言いますが、どうしたらよいのでしょうか。 【A】 朝出掛けに子どもにぐずられ、登園を渋られることは親として辛いことと思います。 お母さんがゆったりした態度でお子さんと向き合い相手になって遊んだり、話しを聞いてやる中で、 登園を渋る原因を探してみてください。4歳になると保育園生活の長い子には親しい友だちの グループができる頃なので、その中に入れないのかも知れません。また、お母さんに自分の方を向いて 相手をして欲しいのかも知れません。子どもの言いなりになってけじめのない対応は逆効果です。 一度保育園の先生に相談してみてください。 ◆◇ワンポイントアドバイス◇◆ 子育てをしていると、ちょっとした事で親は一喜一憂するものです。 保育園や幼稚園に通うお子さんをお持ちの方は、その喜びや心配事など、親だけのものにしないで 保育園や幼稚園の先生に伝えることが大切です。家での様子や園での様子を伝え合う中でお子さんに 対する共通理解を深め、お互い信頼関係がもてるようになると、困った事がおきても解決の糸口が みつけやすくなり、自然にお子さんも心が安定し元気に園生活を過ごすことができるようになるでしょう。 ページの先頭に戻る |