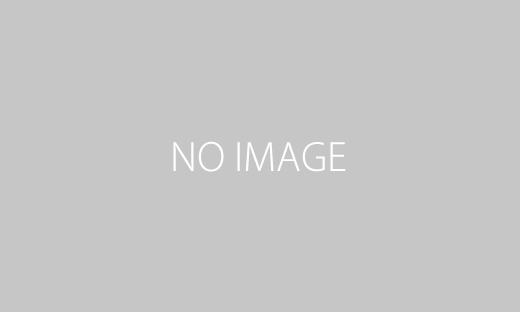子育て・家庭教育相談担当者研修会Ⅱ(実施報告)
実施日:令和5年11月28日(火)
事 業 報 告
「叱られずにいられないのにはわけがあります」~誰かを「叱る」可能性のあるすべての人へ~
「𠮟る」という行為のメカニズムについて知り、相談員や支援者としての対応力を高めることを目的としてYouTubeライブ配信で実施しました。市町村子育て・家庭教育担当者のみならず、学校の先生や放課後児童クラブ等の関係者を中心に238名が受講しました。
【講演】「<𠮟る依存>からの脱却~誰もが生きやすい社会を目指して~」
【講師】一般社団法人子ども・青少年育成支援協会
代表理事 村中 直人 氏
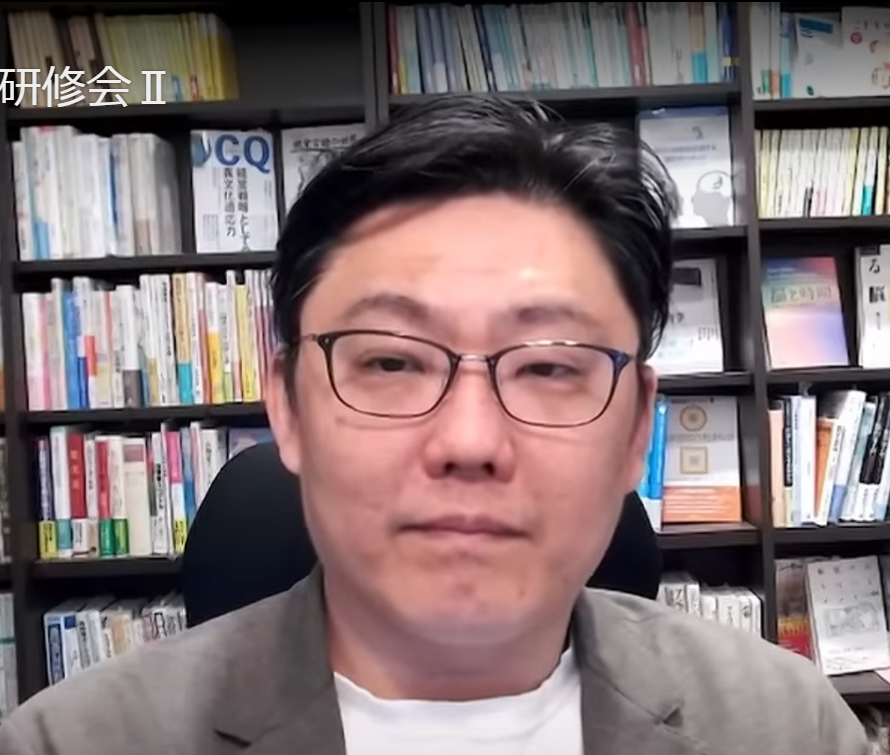
<講演要旨>
◆①<𠮟る依存>とは何か
叱ることで自己効力感、処罰感情(悪いことをした人に罰を与えることで報酬系回路が働き、快感や充足感を得る)が充足される。人は、快楽のために依存するのではなく、苦しみを取り除いてくれるものに依存する。「叱らずにいられない」は受け入れがたい現実からの逃避という意味で依存症に似ていることから<𠮟る依存>と名付けた。
②「叱る」の科学
「叱る」とはネガティブな感情体験を与えることで、相手の行動や認識の変化を引き起こし、思うようにコントロールしようとする行為であり、「相手のため」というタグはつかない。「怒る、罰、叱る」の違いは、叱る側の状態や方法の違いに過ぎず、叱られる側にとっては何も違いがない(脳が区別していない)。「叱る」をできるだけ避けた方がよい理由は倫理的、道徳的なものではなく、単純に効果がないから。人は叱られると、反射的に「防御モード」になる。「防御モード」とは知性や理性を抑えて反射的な行動を引き起こす、人の学びや成長とは真逆のシステムである。叱られる原因には意識が向いていないのに、叱る側は叱られる側が学んだと勘違いする。人から強制された我慢や苦痛では、人は強くならない。自分で選んでやりたいことのためにする我慢が人を強くする。我慢を強制されると、学習性無力感に陥り、未来の扉を準備しても前に進めない人になってしまう。
③<𠮟る依存>を予防する
「叱る」と「ほめる」を行動の後にすることを「後さばき」と言う。<𠮟る依存>の予防に大切なのは、行動の前の環境整備や対応をする「前さばき」である。「前さばき」がうまくなるためには、自分が、「相手に求める『あるべき姿』を決める権力者」であることの自覚が必要。「あるべき姿」は人によって違っていて当然であり、その多様性を理解することが大事。「しない」のか「できない」のかの見極め、また、「できない」を「できる」視点に変えていくことが重要。人間が最も学び、成長するのは、「やりたい」「ほしい」というワクワクした気持ちと困難を乗り越えるための試行錯誤に満ちた「冒険モード」。このモードになるためには、「自己決定」というスイッチが必要。「防御モード」と「冒険モード」は脳の仕組み上、同時に起きないので、「冒険モード」で過ごす時間が長くなれば「防御モード」の時間が短くなる。つまり、「叱る」を手放すことが、自発的・自立的な学びや成長に自然につながっていく。"叱っちゃダメ”と考えるより、どうすれば「冒険モード」に入れるかを考えていくことが、「叱る」を手放す上で重要である。
【質疑応答】
◆発達障がい傾向で素直に指示を聞けない小学生の子どもに、理由を示しながら助言するのも、子どもにとって不快ならば叱ることにあたってしまうのか。
➡「叱る」と「フィードバック」は違う。問題は、支援者の考える「あるべき姿」へ導くことをやりすぎると単なる「叱る」になる。"叱っちゃダメ”なのではなく、叱ったところで達成できないということがまず前提としてある。素直に指示を聞けないことと発達障がいに関連性はあるが、直接的な因果関係はない。今までの体験の中で素直に指示が聞けなくなるような状況が続いているからであり、それは定型発達も発達障がいの子も同じ。発達障がいの子は、その子なりのあたり前や当然をたくさん無視され、否定されてきたからそうなっている。まずは、支援者が思う正しい道に導く前に、その子はどう思っているか、どう感じているか、その子なりの感覚の世界を拾ってあげることが、「叱る」を手放しながら、かつ、良い状況に導いていくことが大事。
◆個が集まった集団に対して、<𠮟る依存>に陥りそうな場面に遭遇したら、どのような対応をしたらよいか。
➡<𠮟る依存>が発生しやすい空間や集団の条件は、「密室性が高いこと」、「そこにある権力格差、権力勾配が非常に大きいこと」。この2つの条件を満たした空間では、人格の問題とか人間としての優劣の問題ではなく、処罰感情が刺激されて、<叱る依存>化する確率が高い。これを集団の中で予防するには、個人の心がけだけでは足りない。外の目が入るようにして密室性を弱めること、自分が持っている権限を子どもたちに委ねていくこと、この2つを油断なくやっていると<叱る依存>は、確実に少なくなっていく。
【受講者の声】
〇「怒る」とは区別して叱っているから大丈夫だと自分に言い聞かせる毎日だった。 でも、叱られる側にとっては、怒られることと叱られることに違いはないという言葉に、頭を殴られたような衝撃を受けた。
〇叱るより褒めて伸ばす教育が以前流行したが、実践しようとしてもうまくいかなかったり、理論がしっくりこなかったりする感じがあった。叱ることでしか相手を動かせない、相手の多様性を認めることができない支援はよくないことがよく分かった。
〇教育現場の研修でも多様性や包括性についてお話を聞くことが多くなってきた。いかに私たちが多様性を受け入れ、その上で、学びと成長を促すことができるかということが重要となってくるのだと感じた。
【受講者の評価】
A (有意義) 80.4%
B (どちらかといえば有意義) 18.6%
C (どちらかといえば有意義でない) 1%
D (有意義でない) 0%
【担当者から】
科学的に明らかにされていることが多い現代において、指導する側がアップデートしていかなければならないことが多くあると感じました。自分と「あるべき姿」が違う人(多様性)を受け入れることが、子育て・家庭教育支援だけではなく、社会全体に必要なことではないかと思いました。